PCIeとは? レーン数やスロットについて、PCIとの違いを解説
- 半導体用語集
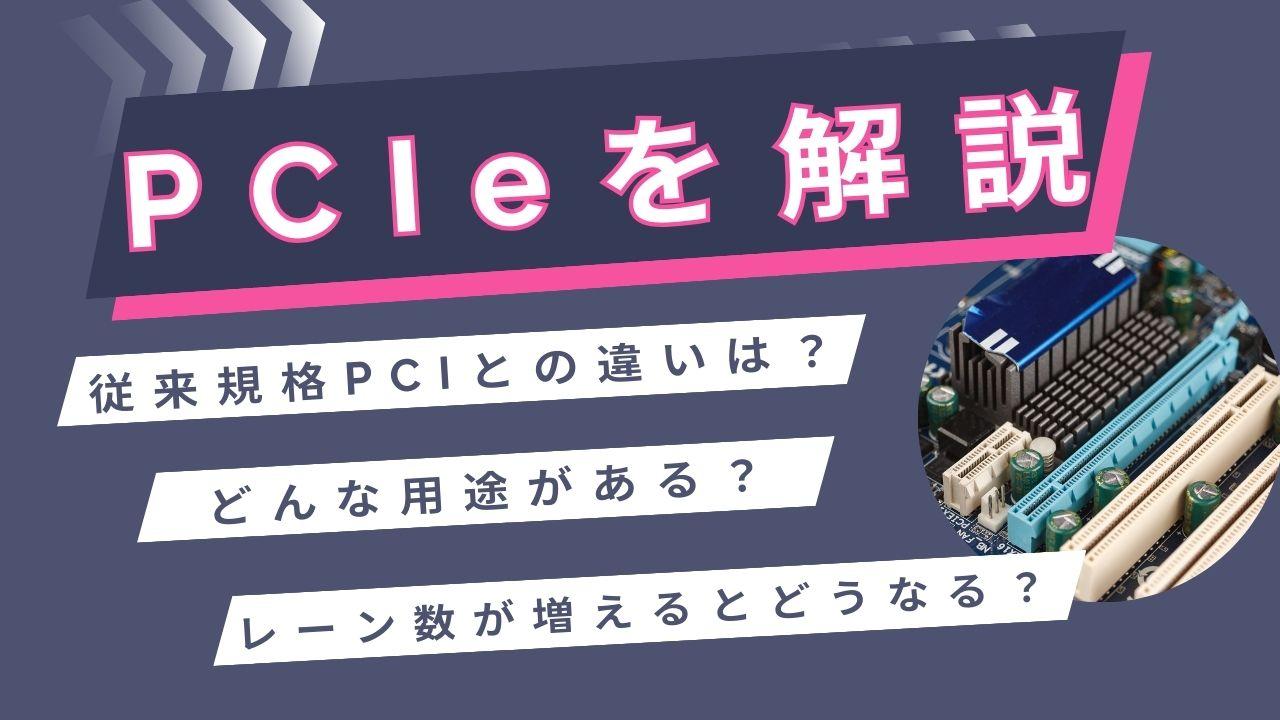
PCIeは、コンピュータの性能や拡張性を大きく左右するインターフェース規格です。グラフィックカード、ネットワークカード、NVMe SSDなどの周辺機器をマザーボードに接続し、高速で安定した通信を可能にします。
従来のPCI規格に比べ、シリアル通信により性能を大幅に向上させたPCIeは、現在ではデスクトップPCやサーバーなど多くの分野で標準規格になっています。
本記事では、その特徴や用途について詳しく解説します。
PCIeとは
PCIeは、コンピュータの内部で高速通信を行うためのインターフェース規格です。主にマザーボードと拡張カードを接続するために使用されます。
例えば、画像処理性能を向上させるグラフィックカードや、高速な有線LANやWi-Fi接続を追加するネットワークカード、高品質な音響処理を実現するサウンドカードなどがあり、さまざまなデバイスと接続可能です。
PCIeは「Peripheral Component Interconnect Express」といい、「周辺機器(Peripheral)」「相互接続(Interconnect)」「高速(Express)」を組み合わせた名前です。外部デバイスとコンピュータを効率的に接続する目的を表しています。
そして、従来のPCIより高速かつ効率的な通信を実現することを「Express」で強調しています。
従来規格のPCIとは
1990年代に登場したPCI(Peripheral Component Interconnect)は、コンピュータのマザーボード上で、拡張カード(周辺機器)を接続するために使用されるインターフェース規格の1つです。
コンピュータの拡張性を向上させるための標準規格として広く普及しました。
PCI普及の歴史
PCIは、1990年代初頭にIntel社によって開発されたコンピュータ拡張スロットの規格です。当時の既存技術が抱える課題を解決し、画期的な拡張性を提供する製品になりました。
1980年代は、IBM社が開発したISAが主流でした。しかし、低速(最大8MB/s)で手動設定が必要という課題があり、利便性に欠けていました。その後、EISAやVESAローカルバスが登場しましたが、高コストや用途の限定性から広く普及するには至りませんでした。
こうした状況の中で、CPUや周辺機器が進化し、より高速かつ使いやすい規格が求められるようになりました。そこで、Intel社は1992年、これらの課題を解決するためにPCI規格を設計し、1993年に正式リリースしました。
PCIは、32ビットまたは64ビットのバス幅(一度に転送できるデータ量)と最大133MB/sのデータ転送速度を備え、ISAやEISAを大幅に上回る性能を実現しました。さらに、プラグアンドプレイ機能を備え、手動設定が不要で自動的にデバイスを認識するという利便性も提供しました。
また、PCIはオープン規格として策定されたため、ハードウェアメーカーが容易に対応製品を開発できる環境が整い、コストの削減と互換性の向上につながりました。その結果、PCIは瞬く間に市場に普及していきました。
しかし1990年代後半になると、デバイスのデータ処理能力が向上し、グラフィックカードやストレージ、ネットワークカードなどの高速なデータ通信を必要とするデバイスが増え始め、PCIの性能では不十分となる場面が増えてきました。
そこで、この課題を解決するために、2000年代にPCI Express(PCIe)が登場しました。PCIeはPCIの後継規格として設計され、従来の並列通信ではなく、シリアル通信を採用することで性能を飛躍的に向上させました。
PCIeの特徴
レーンによるシリアル通信
PCIeは、シリアル通信を採用し、高速なデータ通信を行います。通信の基本単位である「レーン」を複数使用できる仕組みが特徴で、用途に応じた柔軟な拡張が可能です。
シリアル通信とは、データを1ビットずつ順番に直列で送る方式で、イメージとしては「片方向1本ずつの車線」を使ってデータを送るようなものです。レーン数が多い(x4、x8、x16)ほど車線が増え、一度に送れるデータ量が増加します。
1レーンは送信用と受信用の信号線で構成されており、必要な帯域幅に応じてレーン数を増やせます。この仕組みにより、グラフィックカードや高速ストレージのような高性能デバイスの性能を最大限に引き出せます。
PCIeのバージョン
PCIeにはバージョンがあり、アップグレードされるごとに通信速度が向上されています。
以下の表に、各バージョンごとの帯域幅をまとめました。片方向の帯域幅ですが、PCIeはすべて二重通信に対応しているため、実際の総帯域幅は倍になります。
| 世代 | リリース年 | 帯域幅(x1) | 帯域幅(x16) |
| PCIe 1.0 | 2003年 | 250MB/s | 4GB/s |
| PCIe 2.0 | 2007年 | 500MB/s | 8GB/s |
| PCIe 3.0 | 2010年 | 1GB/s | 16GB/s |
| PCIe 4.0 | 2017年 | 2GB/s | 32GB/s |
| PCIe 5.0 | 2019年 | 4GB/s | 64GB/s |
| PCIe 6.0 | 2022年 | 8 GB/s | 128 GB/s |
PCIeの新しいバージョンは古いバージョンとの互換性を持っています。
例えば、PCIe 5.0デバイスをPCIe 3.0スロットに差し込むと動作しますが、帯域幅はPCIe 3.0に制限されます。そのため、ハードウェアをアップグレードしたり、新しいデバイスを導入したりする際の手間が軽減されます。
ポイントツーポイント接続
PCIeはポイントツーポイント方式を採用しており、各デバイスが独自のレーンと帯域を確保しています。
ポイントツーポイント方式により、従来のPCIのように複数のデバイスが1つのバス(通信経路)を共有することで発生する競合を防ぎ、通信効率と安定性が向上しています。
PCIeのバージョン別の特徴
各バージョンの特徴を詳しく解説します。
PCIe 1.0(2003年)
・初めて登場したPCI Express規格
・旧来のPCIやAGPに比べ、シリアル通信方式により効率的なデータ転送が可能に
PCIe 2.0(2007年)
・バックワードコンパチビリティを維持しながらも、高速化によるパフォーマンス向上を実現
・グラフィックカードやSSDなどの高性能デバイスへの対応強化
PCIe 3.0(2010年)
・エンコーディング方式を改良し、効率の向上(8b/10b方式から128b/130b方式へ)
・より低遅延でのデータ転送が可能となり、サーバー用途や高速ストレージデバイスの発展に寄与
PCIe 4.0(2017年)
・NVMe SSDなどのストレージ性能向上に大きく貢献
・サーバーおよびデータセンター向けのインフラ強化にも活用
PCIe 5.0(2019年)
・高性能なAI計算、データセンター、HPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)用途での利用が進む
・高速ネットワークインターフェースや最新GPUとの連携を強化
PCIe 6.0(2022年)
・PAM4(4値パルス振幅変調)技術を採用し、データ転送効率を向上
・データセンターやAI、高速ストレージのさらなる進化に対応
PCIeの用途
PCIeはさまざまな用途があるので、その一部を紹介します。
1. グラフィックカード(GPU)の接続
映像処理やグラフィックスレンダリングを高速化します。ゲームや動画編集、3Dモデリング、AI計算など、計算負荷の高い作業を効率化することが可能です。
2. ストレージデバイス(NVMe SSD)の接続
データの保存や読み書き速度を高速化します。パソコンの起動時間を短縮し、大容量データを迅速に処理が可能です。
3. ネットワークカード(NIC)の接続
高速なインターネット接続やネットワーク通信を実現します。データセンターやオンラインゲーム、ライブストリーミングなどに使用できます。
4. サウンドカードの接続
高品質なオーディオ出力や入力を提供します。音楽制作、映画鑑賞、ゲームでの臨場感あるサウンド体験を向上させます。
5. キャプチャカードの接続
映像信号を取り込んで録画やストリーミングを実現します。ゲーム配信、ライブ配信、ビデオ編集などに利用できます。
6. AIアクセラレーターの接続
AI計算や機械学習を高速化するための専用カードを接続すれば、データセンターや自動運転技術、ディープラーニングに活用できます。PCIeの大容量帯域を活かした並列処理が可能です。
7. FPGA(Field Programmable Gate Array)の接続
高速データ処理やカスタムハードウェアの開発用途に利用可能です。金融業界、5G通信、画像認識技術などの先端分野で活用されます。
8. 外部デバイスの拡張(eGPUなど)
外付けGPU(eGPU)をノートPCに接続し、グラフィック性能を向上させます。外部ストレージ、RAIDアレイなどの高速データ転送が可能です。
PCIeスロットはどこにある?
PCIeスロットは、グラフィックカードやSSD、Wi-Fiカードなどの部品を差し込むための「差し込み口」です。
マザーボードを見ると、中央付近や下部に横向きの細長いスロットが並んでいます。それぞれのスロットには、差し込めるデバイスの大きさや用途に応じて、以下のような種類があります。
x1スロット:小さいスロットで、Wi-Fiカードやキャプチャカード用
x16スロット:大きなスロットで、グラフィックカード用
スロットには「x1」「x4」「x8」「x16」といった表記がされていることが多いので、どのスロットに何を差し込むべきかがわかりやすくなっています。
例えば、ゲームをするためにグラフィックカードを追加したい場合、スロットにカードを差し込むだけで、コンピュータがそのカードを認識して動作します。



