半導体デバイスのFPGAとは? CPUやマイコンとの違い
- 半導体用語集
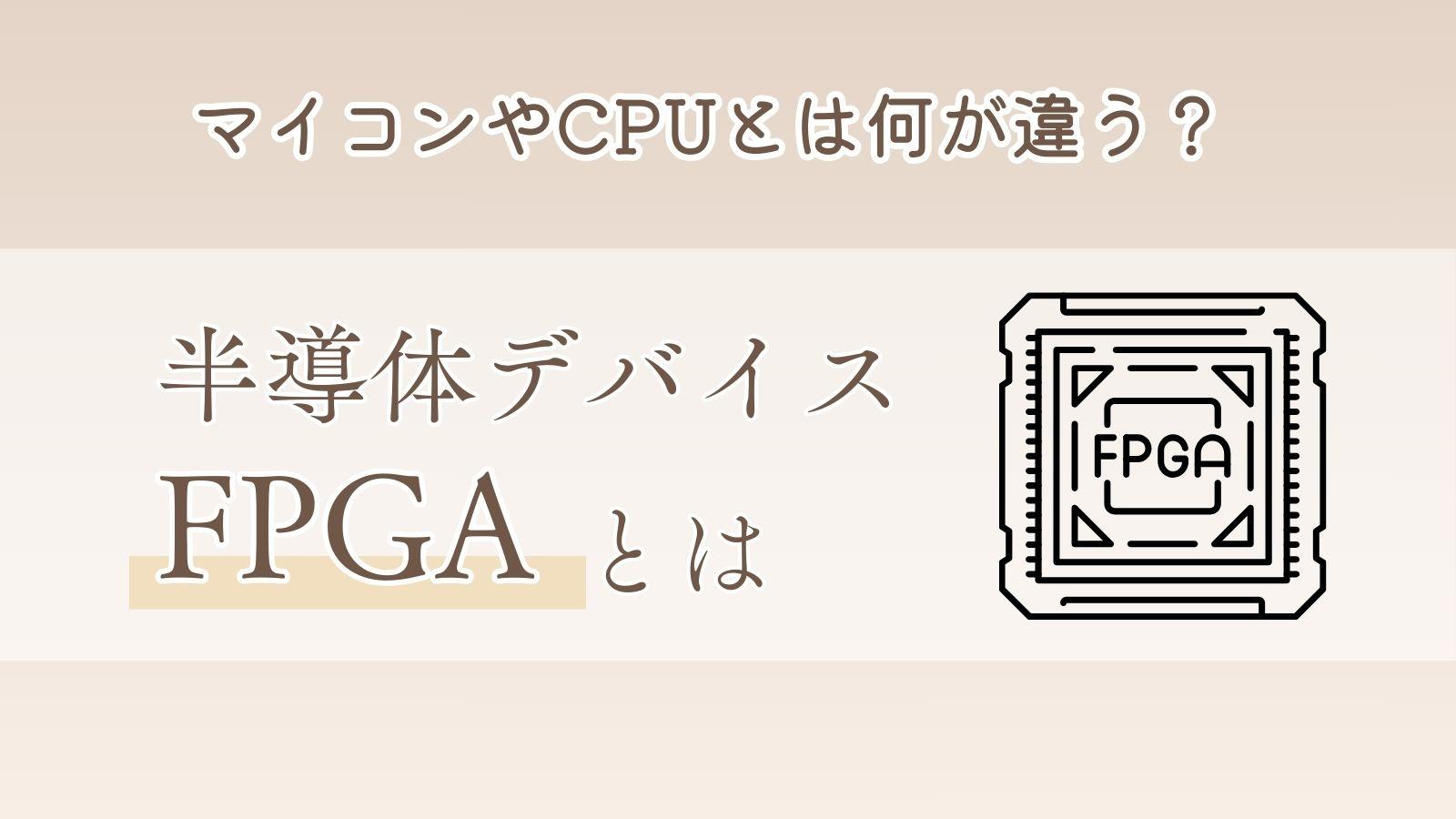
FPGAとは? 特徴・用途について
FPGA(Field Programmable Gate Array:フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)とは、ユーザーが自由に回路構成を変更できる半導体デバイスです。
あらかじめ機能が固定されているCPUやマイコンとは異なり、FPGAはチップ内部の論理回路を後からプログラムによって再構成できるため、「ハードウェアをソフトウェアのように書き換えられる」ことが大きな特徴です。
具体的には、演算回路や制御回路を利用者が定義し、並列に動作させることができます。そのため、汎用CPUが得意とする順を追った処理に比べ、画像処理や信号処理、暗号処理といった並列性の高い演算では、FPGAの方が高速で動作します。
また、ASIC(専用集積回路)のように製造工程で機能を固定する必要がなく、用途に応じて柔軟に設計を変更できる点もメリットです。
用途は幅広く、通信インフラやデータセンターにおける高速演算処理、AI推論やディープラーニングの加速、自動車の先進運転支援システム(ADAS)、医療機器、産業機器の制御、さらには宇宙・航空分野など多岐にわたります。
特に近年は、クラウドサービスにおいてFPGAを活用する動きもあり、ユーザーが専用ハードウェアを持たずとも高速処理を利用できる環境が整いつつあります。
つまりFPGAは、「汎用性」と「高速処理」を両立できる再構成可能な半導体として、CPUやマイコン、ASICと並ぶ重要な選択肢となっています。
FPGAのメリットとデメリット
FPGAは柔軟で強力な半導体デバイスですが、万能というわけではありません。FPGAを採用する際に知っておくべきメリットとデメリットを整理します。
メリット
高速な並列処理が可能
FPGAは内部の回路を自由に構成できるため、複数の処理を同時並行で実行できます。
画像処理や暗号化、信号処理など並列演算が重要な分野では、CPUよりも大幅に高速な処理が可能です。
柔軟な再構成
製造後でも回路を書き換えられるため、用途や要件の変更に応じて設計を更新できます。試作段階での検証や、製品出荷後のアップデートにも活用できる点は大きな強みです。
専用チップに近い性能
ASIC(専用集積回路)ほどではないものの、FPGAはアプリケーションに合わせた最適化が可能です。そのため、ソフトウェア処理では不十分なケースでも、専用チップに近い性能を比較的短期間で実現できます。
ハードウェアレベルでの制御
OSやドライバを介さず、ハードウェアレベルで直接処理を行えるため、低レイテンシが求められるシステムに適しています。
デメリット
開発難易度が高い
FPGAは回路設計の知識が必要で、CPUやマイコンに比べて開発ハードルが高くなります。ソフトウェアエンジニアが扱うには学習コストが大きい点が課題です。
消費電力が大きい場合がある
同じ機能を実現する場合、FPGAは最適化されたASICに比べて消費電力が大きくなる傾向があります。モバイル機器など電力制約が厳しい用途には不向きなケースもあります。
コストが高い
FPGAは少量多品種の利用には適していますが、量産時のコスト効率はASICに劣ります。そのため、大規模に普及する製品には採用しにくいことがあります。
実行速度の限界
並列処理には強い一方で、クロック周波数そのものはCPUやASICほど高くないため、逐次処理には向かない場合もあります。
FPGAの基本構造と仕組み
FPGA(Field Programmable Gate Array)は、チップ内部に多数の小さな論理ブロックと配線リソースを持ち、それらを組み合わせることで任意のデジタル回路を構成できる半導体デバイスです。
基本構造と仕組みを解説します。
基本構造
FPGAは主に以下の要素から構成されています。
論理ブロック(CLB: Configurable Logic Block)
FPGAの中核となる要素で、LUT、フリップフロップ、組み合わせ回路などを含みます。
LUTは「真理値表のような小規模なROM」であり、任意の論理関数を実現できます。
配線リソース
各論理ブロック同士を自由に接続するためのスイッチや配線網です。
再構成可能な配線こそが、FPGAの柔軟性を支える仕組みです。
入出力ブロック(I/O Block)
外部デバイスやメモリ、センサー、プロセッサと信号をやりとりするためのインターフェース部分です。
多様な通信規格(PCIe、Ethernet、DDRメモリなど)に対応できる場合があります。
組み込みハードウェア機能
近年のFPGAには、DSPブロック(乗算器などの演算回路)、メモリブロック(BRAM)、さらにはARMコアなどのプロセッサを内蔵したSoC FPGAも存在します。
動作の仕組み
FPGAの動作は大きく以下のステップで進みます。
設計記述
ハードウェア記述言語(HDL:VHDLやVerilog)や高位合成ツールを用いて、回路の動作をコードで定義します。
論理合成と配置配線
記述された論理をFPGA内部のLUTやフリップフロップに割り当て、配線リソースで接続するプロセスです。専用のEDAツールを使用します。
コンフィギュレーション
合成結果をビットストリームとしてFPGAに書き込み、回路が実際に構成されます。
必要に応じて、再度ビットストリームを書き込むことで構成を変更可能です。
FPGAとCPUの違い
FPGAとCPUはどちらも電子機器の頭脳として利用されますが、その仕組みや得意分野は大きく異なります。両者の特徴を比較しながら違いを整理します。
処理方式の違い
CPUは命令を順を追って実行する「汎用プロセッサ」です。
1つの演算ユニットを中心に、ソフトウェアで書かれたプログラムを順番に処理します。マルチコアCPUでも基本は逐次処理の拡張にすぎません。
FPGAは内部の論理回路を自由に組み合わせられるため、複数の処理を並列で同時に実行できます。同じ処理を繰り返す演算や、信号処理のような並列性の高い処理では高い性能を発揮します。
柔軟性と専用性の違い
CPUは最初から汎用的な命令セットを備えており、OSやアプリケーションを動かすための一般的な仕組みが整っています。
どんな処理にもある程度対応できる一方で、特定の用途に最適化することは難しいという制約があります。
FPGAは利用者が回路自体を設計できるため、用途に合わせて最適化したハードウェアを構築できます。その結果、特定のタスクにおいてはCPUよりも高速かつ効率的に処理できることがあります。
開発の違い
CPU向け開発はC言語やPythonといった高級言語を使い、ソフトウェア開発の知識があれば比較的容易に行えます。
FPGA開発はハードウェア記述言語(VHDL、Verilog)や専用ツールを使い、回路設計の知識が必要です。そのため学習コストは高いものの、得られる成果は「専用ハードウェアを短期間で実現できる」点にあります。
性能・電力効率の違い
CPUはクロック周波数が高く、単純な逐次処理では優れていますが、大量の並列演算では効率が落ちます。
FPGAは並列処理を活かすことで特定分野ではCPUを圧倒する性能を出せますが、一般的な用途では電力効率やコスト面で不利になる場合もあります。
FPGAとマイコンの違い
FPGAとマイコンはいずれも電子機器に広く使われていますが、その役割や特徴は大きく異なります。
ここでは両者の違いをわかりやすく解説します。
仕組みの違い
マイコン(マイクロコントローラ)は、小型のCPUにメモリや周辺回路(タイマー、UART、ADCなど)を組み込んだ「ワンチップの制御用コンピュータ」です。ソフトウェアでプログラムを記述し、順次処理によって制御や演算を行います。
FPGAは固定のCPUを持たず、内部の論理回路をユーザーが自由に設計して動作させます。つまり「ソフトウェアで命令を実行する」マイコンに対し、FPGAは「ハードウェアそのものを作り変えて処理する」仕組みです。
得意分野の違い
マイコンは、センサーの読み取りやモーター制御、家電の操作など、比較的単純で順を追った制御タスクに向いています。低消費電力で安価なため、組み込み機器に最適です。
FPGAは、高速な並列演算やリアルタイム処理を必要とする分野に強みがあります。例えば、画像処理、通信信号処理、AI推論などではマイコンよりもはるかに高い性能を発揮できます。
開発とコストの違い
マイコンはC言語やArduinoのような高級言語で簡単に開発できるため、初心者からプロまで幅広く扱えます。また、安価に入手できる点も普及の理由です。
FPGAはハードウェア記述言語や専用ツールが必要で、開発難易度は高めです。
デバイス自体も高価になる傾向があり、少量多品種や試作用途には適していますが、大量生産品ではコスト面で不利になることがあります。



