核融合発電とは? メリット・実用化に向けた課題
- 最新動向
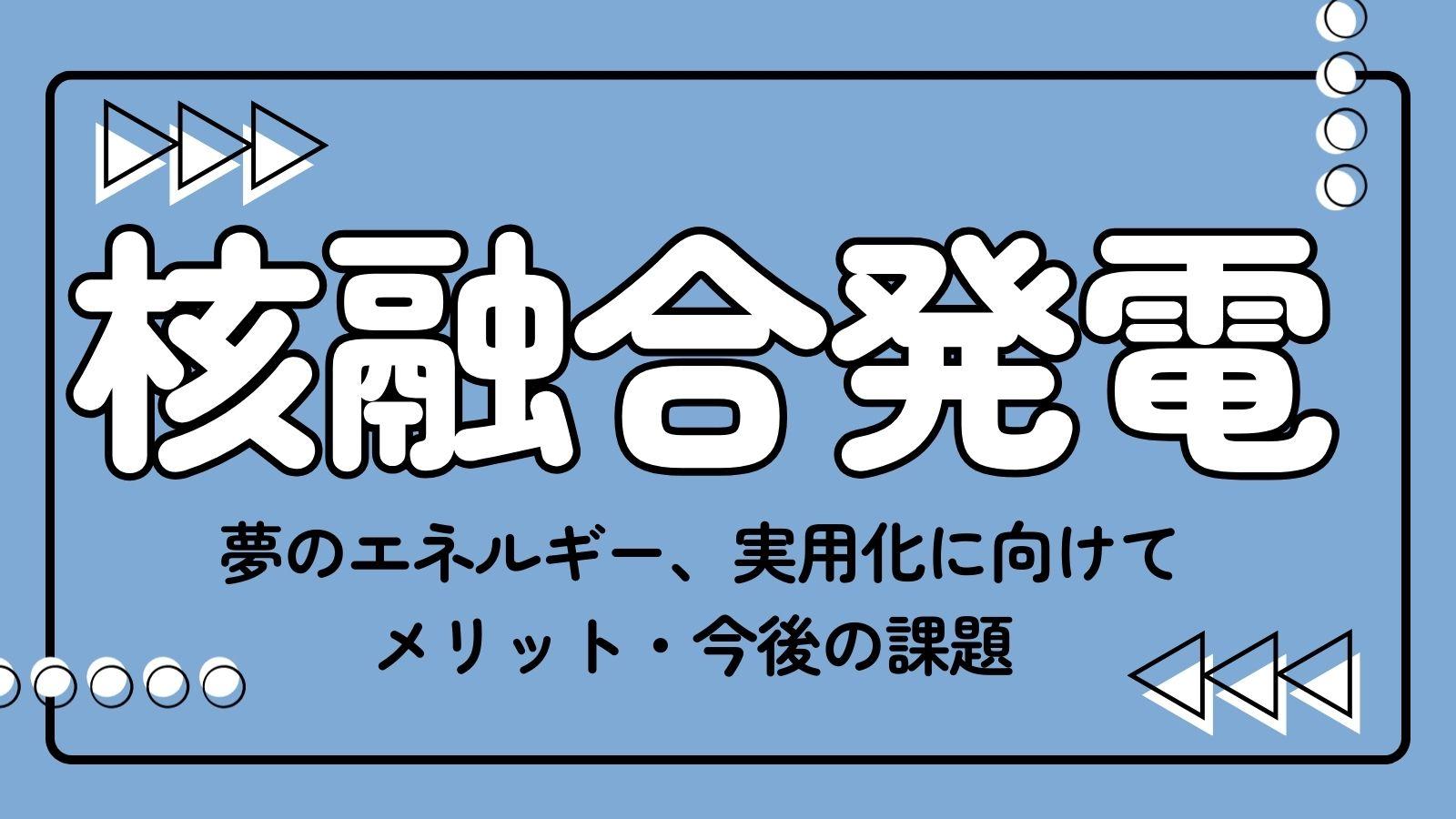
核融合発電とは? 利用するメリット
核融合発電とは、軽い原子核同士を融合させてエネルギーを取り出す発電方法です。太陽や恒星が光と熱を放出しているのも、この核融合反応によるものです。
核融合発電は、現在の原子力発電(核分裂)と比べていくつかの大きな特徴があります。
温室効果ガスを排出しないクリーンエネルギー
核融合反応では二酸化炭素や窒素酸化物などの温室効果ガスは一切発生しません。火力発電に代わる脱炭素型の電源として、気候変動対策に大きく貢献します。
燃料が豊富で枯渇の心配がない
燃料となる重水素は海水に豊富に含まれ、理論的には長期間で提供可能なエネルギー量があります。
三重水素は装置内でリチウムから生成でき、資源供給リスクが極めて低いのも魅力です。
高い安全性
核融合反応は、1億度以上のプラズマを維持するという特殊な条件下でのみ進行します。
装置が故障すると自然に反応が停止するため、暴走事故やメルトダウンのリスクが極めて低いのが特徴です。
放射性廃棄物が少ない
核分裂発電に比べ、生成される放射性廃棄物は少量で、かつ寿命が短いものが中心です。
長期的な保管や地層処分の負担が軽いため、社会的な合意形成が比較的容易です。
安定した大規模電源として期待
太陽光や風力と違い、理論的には天候に左右されず安定したベースロード電源となる可能性があると期待されています。
再生可能エネルギーと組み合わせることで、より持続可能なエネルギーミックスを実現できます。
核融合発電は「クリーンで安全な未来のエネルギー源」として期待されていますが、超高温のプラズマを安定的に閉じ込め続ける技術や、発生する中性子に耐える材料の開発など、解決すべき課題も多く、世界中で研究開発が進められています。
核融合発電の仕組み
核融合発電の基本的な流れは火力発電や原子力発電と同じで、熱で水を沸かして蒸気を作り、タービンを回して発電します。
ただし、熱の発生源がまったく異なります。
1. 燃料と核融合反応
燃料として使われるのは、主に重水素(D)と三重水素(T)です。
これらを混ぜ合わせて、超高温に加熱します。すると原子核同士が反発力を超えて融合し、ヘリウムと高速中性子が生まれます。
このときに莫大な熱エネルギーが放出されます。
2. プラズマの生成と閉じ込め
核融合反応を起こすためには、燃料をプラズマ状態にして閉じ込める必要があります。代表的な方法は次の2つです。
● 磁場閉じ込め方式(トカマク型、ヘリカル型)
ドーナツ型の装置の中に強力な磁場を作り、プラズマを浮かせるように閉じ込めます。
現在の国際熱核融合実験炉(ITER)もこの方式を採用しています。
●慣性閉じ込め方式(レーザー核融合)
小さな燃料ペレットに高出力レーザーや粒子ビームを一斉に照射し、急激に圧縮・加熱して核融合を起こします。
米国のNIF(国立点火施設)がこの研究を進めています。
3. 熱エネルギーから電気へ
核融合反応で発生した中性子は装置の壁に吸収され、ブランケットと呼ばれる部分で熱に変換されます。この熱で冷却材を温め、蒸気を発生させてタービンを回すことで発電します。
核融合発電の実用化に向けての課題
核融合発電は「夢のエネルギー」と呼ばれる一方、実用化には多くの技術的・経済的な課題が残されています。
主な課題は次の通りです。
プラズマの安定制御
核融合を起こすには超高温プラズマを生成し、長時間安定して閉じ込め続ける必要があります。しかしプラズマは不安定で、わずかな乱れでも閉じ込めが崩れ反応が止まってしまいます。
精密な磁場制御技術やリアルタイムのプラズマ制御システムの開発が不可欠です。
材料の耐久性
核融合反応で生じる高速中性子は、装置の壁材料を激しく損傷させます。
長期間耐えられる耐中性子材料や、放射化しても短寿命で安全に廃棄できる材料の開発が大きな課題です。
燃料サイクルの確立
三重水素(トリチウム)は自然界にほとんど存在せず、装置内で生産しながら利用する必要があります。そのためにブランケット内でリチウムからトリチウムを生成し、効率的に回収するトリチウム燃料サイクルの確立が求められます。
エネルギー利得と発電コスト
一部の実験ではエネルギー利得(Q値)が1を超える成果が報告されていますが、持続的に安定して達成できるわけではなく、商業発電に必要とされる高いQ値にはまだ到達していません。
さらに、巨大で高価な装置を経済的に運用できるよう、建設・維持コストの削減が必要です。
商業化までの時間と投資
ITERなどの国際プロジェクトでは、2030年代後半に発電実験を行う計画が示されています。商業炉の稼働は2040年代以降になると見込まれており、技術開発や政策決定の進捗によって時期は前後する可能性があります。
長期的な研究開発投資や、社会がそれを支える体制の整備が欠かせません。
これらの課題を克服することで、核融合発電は初めて実用化に近づきます。
技術の進歩だけでなく、国際協力や産業界・政策面での支援も重要な要素となっています。
日本の核融合発電に関する取り組み
政府の戦略・政策体制
日本政府は、「核融合エネルギー(Fusion Energy)」の実現を加速させるため、国家戦略「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を整備しています。
2025年6月にこの戦略を改定し、安全性・産業化・研究開発のロードマップを明確にしました。
産業協議会(J-Fusion)の設立
戦略の中で、核融合技術を実用・産業化する際の調整機関として、「一般社団法人フュージョンエネルギー産業協議会(通称:J-Fusion)」が設立される見込みです。
官民の連携や規制、安全性の枠組みづくりなどの役割が期待されています。
実用化に向けた発電実証の議論
2030年代の発電実証(パイロットスケールで核融合発電を実際に行う段階)を国策に据えるべく、用地選定やコスト、規制などに関する議論が始まっています。



