オシロスコープとは? 特性や使い方、動作原理を解説
- 半導体用語集
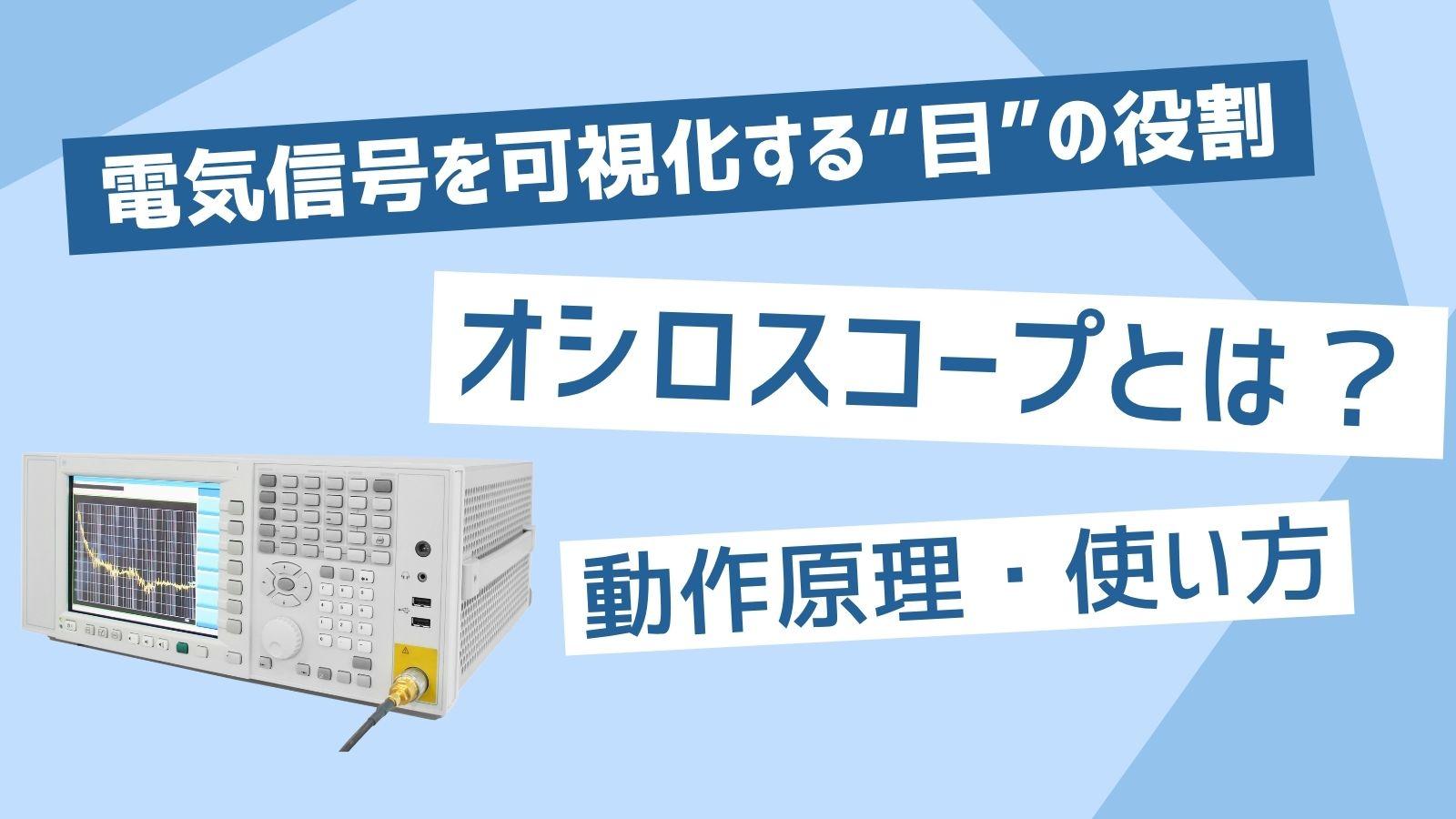
オシロスコープは、電子回路内を流れる電気信号の動きを正確に捉え、波形として表示します。電子機器の動作を目で確認できるツールです。
オシロスコープは、電気信号の時間変化を波形として表示することができ、電子回路の開発や修理、研究においても欠かせません。
本記事では、オシロスコープとは何か?という基本から、主な特性、使い方、動作原理を解説しています。
オシロスコープとは? 特性について
オシロスコープ(Oscilloscope)とは、電気信号の電圧の時間的変化を波形として視覚的に表示する測定器です。電気・電子回路の開発やトラブルシューティングの場面で、信号の状態を見るための基本かつ不可欠なツールとして広く利用されています。
信号を観察することで、例えば回路が正常に動作しているか、予期しないノイズが混入していないか、トランジスタやICが意図したタイミングでスイッチングしているかなどをリアルタイムで評価できます。
オシロスコープは、主に以下のような特性を持っています。
| 概要 | 測定への影響 | |
| 帯域幅 | 測定可能な最大周波数 | 高周波信号や立ち上がりエッジの忠実度に影響 |
| サンプリングレート | 1秒あたりのサンプリング数 | サンプル不足で波形の誤表示(エイリアシング)が起きる |
| 垂直分解能 | 電圧の細かさ(ADCのビット数) | 微小な電圧差の検出能力に関係 |
| メモリ長 | 一度に記録できるサンプル数 | 長波形や高解像度測定で不足すると情報を取り逃す |
| トリガ機能 | 波形を安定表示させるための同期機能 | 条件設定により一過性の波形やノイズを検出可能 |
| 入力インピーダンス | 測定信号に対する負荷 | 測定対象に負担をかけすぎると波形が歪む |
| チャンネル数 | 同時に測定できる信号数 | 信号の相関観測や差分測定に影響 |
| 表示更新レート | 画面上に波形を再描画する速さ(反応性) | 高いほどグリッチや短周期ノイズを検出しやすい |
| 追加機能(解析) | 自動測定、FFT、プロトコルデコードなどの支援機能 | 周波数解析や通信確認などの高次解析が可能 |
また、近年はアナログ方式からデジタル方式へと主流が移り、波形の保存・解析・周波数成分表示(FFT)なども可能になっています。
オシロスコープは、電子工学だけでなく、通信、医療機器、自動車、ロボティクスなどの幅広い分野で利用されており、電気信号の可視化による“目”の役割を果たしています。
オシロスコープの使い方
オシロスコープの基本操作の流れと主要な設定項目をわかりやすく解説します。
1. プローブの接続
まず、測定対象の回路にオシロスコープ用プローブを接続します。
プローブには通常、測定端子(チップ)とグラウンドクリップがあり、次のように接続します。
チップ(先端):測定したい信号ラインに接続
グラウンドクリップ:回路のGND(接地)に接続
※多くのプローブには「×1 / ×10切り替えスイッチ」があり、×10に設定することで回路への負荷を減らし、測定精度を向上させることが可能です。
2. 垂直軸(電圧)の設定
オシロスコープの画面で縦方向(Y軸)は電圧(V)を表します。
画面の1目盛あたりの電圧スケール(V/div)を調整して、波形の高さが適切になるようにします。
例:5V/divに設定 → 画面の1目盛が5Vに相当
3. 水平軸(時間)の設定
横方向(X軸)は時間(t)を表し、波形の時間的な変化を見られます。
スイープ速度(Time/div)を調整することで、1目盛あたりの時間範囲を設定します。
例:1ms/div → 波形の1目盛分が1ミリ秒に相当
4. トリガの調整
波形が不安定で画面上を横に流れてしまう場合は、トリガ設定を行うことで表示を安定させます。
トリガは、波形がどのタイミングで描画されるかを決める機能です。
トリガソース:どのチャンネルを基準にするか
トリガレベル:どの電圧で波形を固定するか
トリガエッジ:立ち上がり(上昇)か立ち下がり(下降)か
5. 複数チャンネルの活用
多くのオシロスコープは複数チャンネルを備えており、異なる信号を同時に比較表示できます。
例えば、入力信号と出力信号の時間差(遅延)や電圧差などを視覚的に把握できます。
6. 波形の読み取りと解析
波形が安定して表示されたら、以下のような情報を読み取ります。
・ピーク電圧、平均電圧
・周波数、周期、デューティ比
・立ち上がり/立ち下がり時間
・ノイズやグリッチの有無
一部のデジタル・オシロスコープには自動測定機能があり、画面上に数値が表示されるものもあります。
オシロスコープの動作原理
オシロスコープは、電気信号の時間的な変化をリアルタイムで表示する測定器ですが、その背後にはアナログ信号の処理、座標変換、タイミング制御といった複雑な仕組みが動作しています。
以下では主にデジタル・オシロスコープを中心に、その基本的な動作原理を解説します。
1. 信号の取り込み(入力段)
被測定回路からの電気信号は、まずオシロスコープのプローブを通して入力されます。
この信号は、以下の処理を経て内部回路に取り込まれます。
アッテネータ回路:信号レベルを調整(×1、×10など)
高入力インピーダンス設計:回路への負荷を最小限に抑える
入力アンプ:微小な信号を増幅して測定可能なレベルに引き上げ
2. サンプリングとA/D変換
次に、入力されたアナログ信号は、サンプリング回路によって一定間隔で取り込まれ、アナログ-デジタル変換(ADC)が行われます。
・サンプリングレートに応じて、1秒あたりのデータ点が決定
・量子化分解能により電圧の細かさをデジタル化
この処理により、信号はデジタル波形データとしてメモリに蓄積されます
3. トリガシステム(同期制御)
波形を画面上で安定して表示させるためのきっかけとなるのが、トリガ機構です。設定された条件(電圧、エッジ、パターンなど)を検出すると、画面の更新を開始します。
エッジトリガ:上昇・下降エッジで同期
パルストリガ:一定幅のパルスを検出
ビデオ・シリアルトリガ:特殊プロトコルにも対応可能
これにより、同じ形の波形が毎回同じ位置に表示されるようになります。
4. メモリとディスプレイ処理
サンプリングされたデジタルデータは、内部メモリに蓄積され、次に波形再構成エンジンによって画面上に描画されます。
・水平方向(X軸):サンプリング時の時刻データにより時間を表現
・垂直方向(Y軸):デジタル化された電圧値をスケーリングして表示
・高速描画によるリアルタイム表示が可能
また、高度なオシロスコープでは複数波形のオーバーレイ表示やヒストグラム表示、スペクトル解析(FFT)などもサポートされています。
5. 追加機能と解析支援
自動測定機能:ピーク値、平均、周波数などを自動算出
カーソル測定:手動で波形上の点を指定して差分測定
ストレージ保存:測定データをUSBやPCに保存可能
マスクテストやパターン解析:製造テストや通信検証に利用



