レギュレータとは? 種類と動作原理、構造、メリット・デメリットを解説
- 半導体用語集
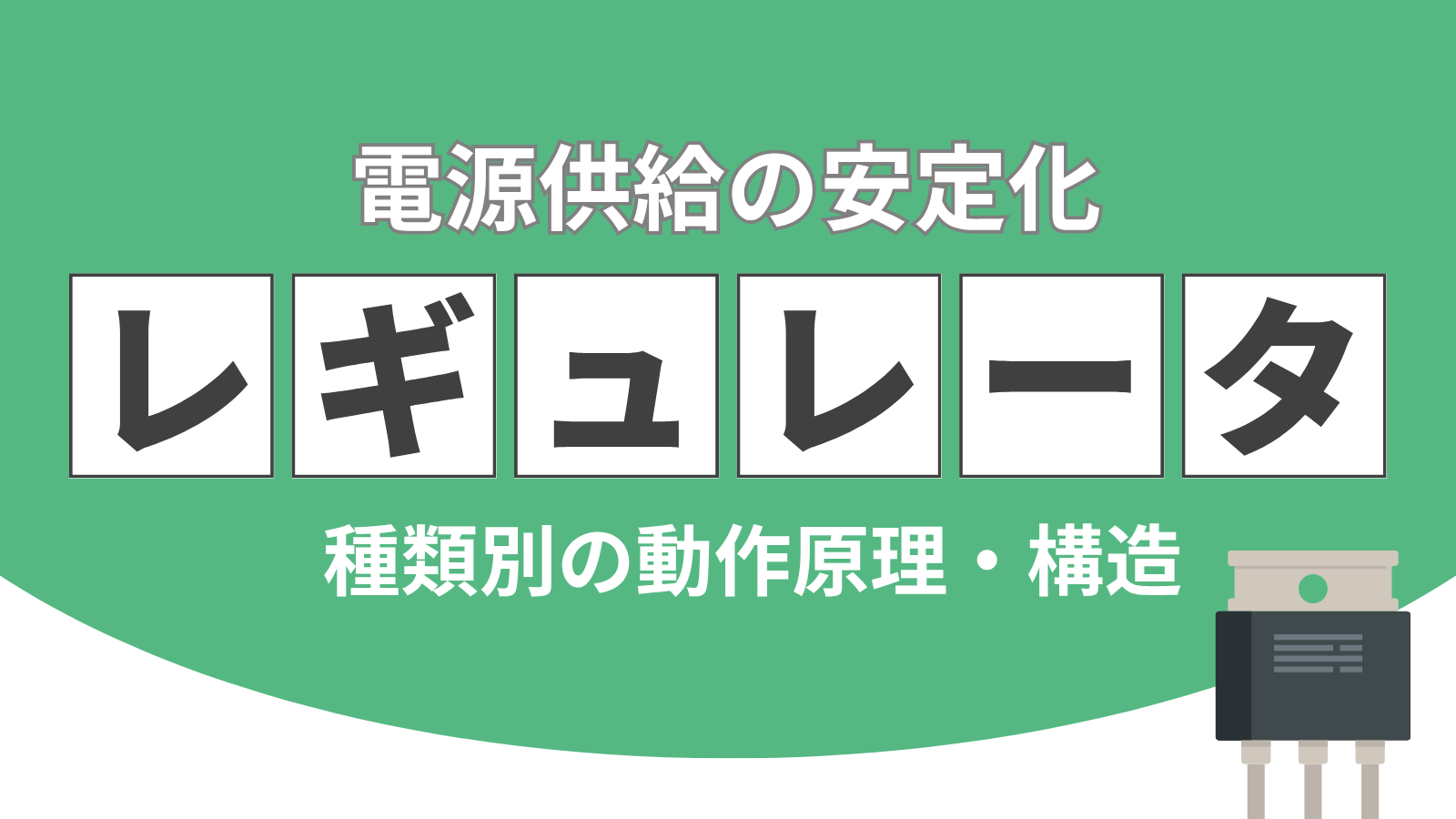
電子回路やデジタル機器の正常な動作を維持するためには、安定した電源供給が欠かせません。しかし、入力電圧はバッテリーの放電や電源ラインのノイズによって容易に変動してしまいます。
そこで重要な役割を果たすのが「レギュレータ」です。レギュレータは、入力電圧が変動しても、一定の出力電圧を安定して供給するための回路です。
本記事では、レギュレータの基本的な役割や、主要なレギュレータの種類に関する構造や動作原理、メリット・デメリットを解説していきます。
レギュレータとは? 役割について
レギュレータとは、電源回路において入力電圧や負荷の変動にかかわらず、安定した出力電圧を供給するための回路やデバイスのことです。
最も基本的な役割は、フィードバック回路を用いて出力電圧を設定値に維持することです。入力電圧の変動や負荷の変動があっても、安定した電圧を供給します。
その他、以下のような役割もあります。
過電圧保護(Overvoltage Protection, OVP)
入力電圧が設定された許容範囲を超えた場合に、回路を保護する機能です。内部の比較回路やクランプ回路が、過電圧を検出した際に出力を遮断または制限します。
バッテリー駆動回路やAC-DCコンバータでは、急激な電圧上昇が発生する可能性があるため、過電圧保護が不可欠です。
過電流保護(Overcurrent Protection, OCP)
出力電流が定格電流を超えた場合に、回路を保護する機能です。内部のシャント抵抗で電流を監視し、過電流が検出されると出力電圧を低下または遮断します。
スイッチングレギュレータでは、インダクタ電流が急激に増加することがあるためOCPが必要です。
過熱保護(Over Temperature Protection, OTP)
内部温度が許容範囲を超えた際に、回路を保護する機能です。
IC内部に温度センサーが内蔵されており、温度が設定値を超えると動作を停止または制限します。
ちなみに、スイッチングレギュレータのMOSFETやLDOレギュレータのバイポーラトランジスタは、熱損失が大きいため、熱保護が必要です。
電源リップル除去
入力電圧に含まれるACノイズやリップル(周期的な変動)を除去し、安定したDC出力を得る機能です。
LDOレギュレータは、スイッチングノイズが少ないためリップル除去能力が高いです。一方、スイッチングレギュレータではインダクタとコンデンサを組み合わせたフィルタ回路でリップルを抑制します。
ソフトスタート機能
電源投入時の突入電流を抑制し、回路を保護する機能です。
出力電圧を徐々に上昇させることで、急激な電流変動を防止します。
バッテリー駆動回路や大電流回路では、突入電流がICやトランジスタを破壊する可能性があるため、ソフトスタートが重要です。
フィードバック制御
出力電圧を常に監視し、目標電圧との差を調整する機能です。出力電圧が目標値より高い場合は出力を減少させ、低い場合は増加させます。
例えば、LDOレギュレータは出力電圧をフィードバック回路で制御し、精密な電圧調整が可能です。
リニアレギュレータの動作原理・基本構造
一般的なレギュレータには、リニアレギュレータとスイッチングレギュレータの2種類があります。
リニアレギュレータは、 入力電圧から不要な電圧を熱として消費して安定した出力電圧を生成する方式です。
構造がシンプルでノイズが少ないですが、効率が低下しやすいという特徴があります。
アナログ回路(オーディオ回路、センサー回路)や、ローノイズが要求される回路、定電圧供給が必要な低電力回路で適用されます。
動作原理
入力電圧と出力電圧の間に制御素子(トランジスタやMOSFET)を挿入し、電圧差を制御して出力電圧を安定化します。
差分は熱として消費されるため、発熱が大きくなります。
基本構造
リニアレギュレータは以下の4つのブロックで構成されています。
1. リファレンス電圧回路
出力電圧の基準となる安定した基準電圧を生成します。
ツェナーダイオードやバンドギャップリファレンス回路が用いられ、温度補償が施されているため外部環境の変化に影響されにくいです。
2. エラーアンプ
出力電圧と基準電圧を比較し、その誤差を増幅して制御信号を生成します。
出力電圧が基準電圧よりも高い:エラーアンプの出力が低下し、トランジスタのオン抵抗が増加すると、出力電圧が低下
出力電圧が基準電圧よりも低い:エラーアンプの出力が増加し、トランジスタのオン抵抗が減少すると、出力電圧が上昇
3. パスエレメント
出力電圧を制御する主要な制御素子です。
トランジスタやMOSFETが用いられ、入力電圧と出力電圧の間で電圧降下を発生させ、安定化を行います。
4. 保護回路
レギュレータを過電流、過電圧、過熱から保護するための回路です。
過電流保護回路:出力電流が設定値を超えると、シャント抵抗で検出し、パスエレメントの動作を制限
温度保護回路:内部温度が設定値を超えると、レギュレータを一時的にシャットダウン
過電圧保護回路:入力電圧が許容範囲を超えた場合、クランプ回路が作動し、回路を保護
メリット
・トランジスタやオペアンプなどの基本部品で構成されており、設計がシンプル
・スイッチング動作を行わないため、スイッチングノイズやEMI(電磁干渉)が発生しない。そのため、アナログ回路やオーディオ回路に適している
・出力電圧の制御がアナログベースで行われるため、電圧変動への応答が速い
・フィードバック回路による安定化が行われるため、出力電圧にリップル成分が少ない
・高周波スイッチング回路の設計が不要であり、回路解析が容易
デメリット
・入力電圧と出力電圧の差が大きい場合、その差分が熱として消費されるため効率が低下する
・高電圧差・大電流出力時には、大量の熱が発生するため、ヒートシンク(放熱対策)が必要
・大電流を供給すると熱損失がさらに増加し、発熱制御が困難になる
・入力電圧が出力電圧よりも高くなければ動作しない(降圧のみ対応)
スイッチングレギュレータの動作原理・基本構造
スイッチングレギュレータは、 トランジスタを高速スイッチングさせることでエネルギーを制御し、効率的に電圧を変換する方式です。
リニアレギュレータと異なり、エネルギーを熱ではなくインダクタやコンデンサに蓄えて制御します。
動作原理
トランジスタをオン・オフ制御(PWM制御) してエネルギーを蓄積し、インダクタやコンデンサを介して出力電圧を安定化します。
出力電圧の調整は、スイッチング周波数やデューティ比を調整することで行います。
基本構造
スイッチングレギュレータは、以下の5つのブロックで構成されます。
1. PWM制御回路
出力電圧を監視し、スイッチング素子のオン時間とオフ時間(デューティ比) を調整して、出力電圧を安定化させます。
2. スイッチング素子
トランジスタやMOSFETを用いて、 オン・オフを高速で繰り返すことでインダクタへの電流供給を制御します。
スイッチON:インダクタに電流が蓄積される
スイッチOFF:インダクタに蓄積されたエネルギーが出力に放出される
デューティ比: 出力電圧の制御はデューティ比
Vout=Vin×D(降圧型の場合)
3. インダクタ
エネルギーの蓄積と放出を行う素子であり、スイッチング時の電流変動を平滑化する役割があります。
インダクタンスは、リップル電流を抑制するために適切に選定されます。
スイッチON:インダクタにエネルギーが蓄積される
スイッチOFF:インダクタのエネルギーが出力側に放出される
4. ダイオード
スイッチング素子がオフの際に、インダクタのエネルギーを出力側に送る経路を提供します。また、逆流防止としての機能もあります。
5. 出力フィルタ
出力端のリップル電圧を低減し、安定したDC電圧を供給します。
コンデンサ: 電圧の平滑化
電解コンデンサ:大容量で低周波リップル除去に適している
セラミックコンデンサ:高速応答が必要な箇所で使用される
インダクタ: ノイズフィルタリングに使用されることもある
メリット
・エネルギーを熱として消費せず、スイッチング動作によって蓄積・放出するため効率が高い
・効率が高いため、入力電圧と出力電圧の差が大きくても発熱が少ない
・降圧、昇圧、昇降圧など、多様な電圧変換が可能
・幅広い入力電圧範囲に対応できる
・高効率のため、大電流供給にも対応可能
・マイコンやデジタル制御で出力電圧やスイッチング周波数を設定できる
デメリット
・高速スイッチング動作によりスイッチングノイズやEMI(電磁干渉)が発生しやすい
・インダクタ、ダイオード、コンデンサなどの外付け部品が必要で、回路面積が大きくなる
・PWM制御のフィードバックが必要であり、アナログ回路と比較して応答が遅れる
・ソフトスタートや保護回路の設計が必要
・スイッチング動作によるリップル成分が出力に現れるため、フィルタ設計が重要



