コンパレータとは? 回路での役割やオペアンプとの違い、用途例について解説
- 半導体用語集
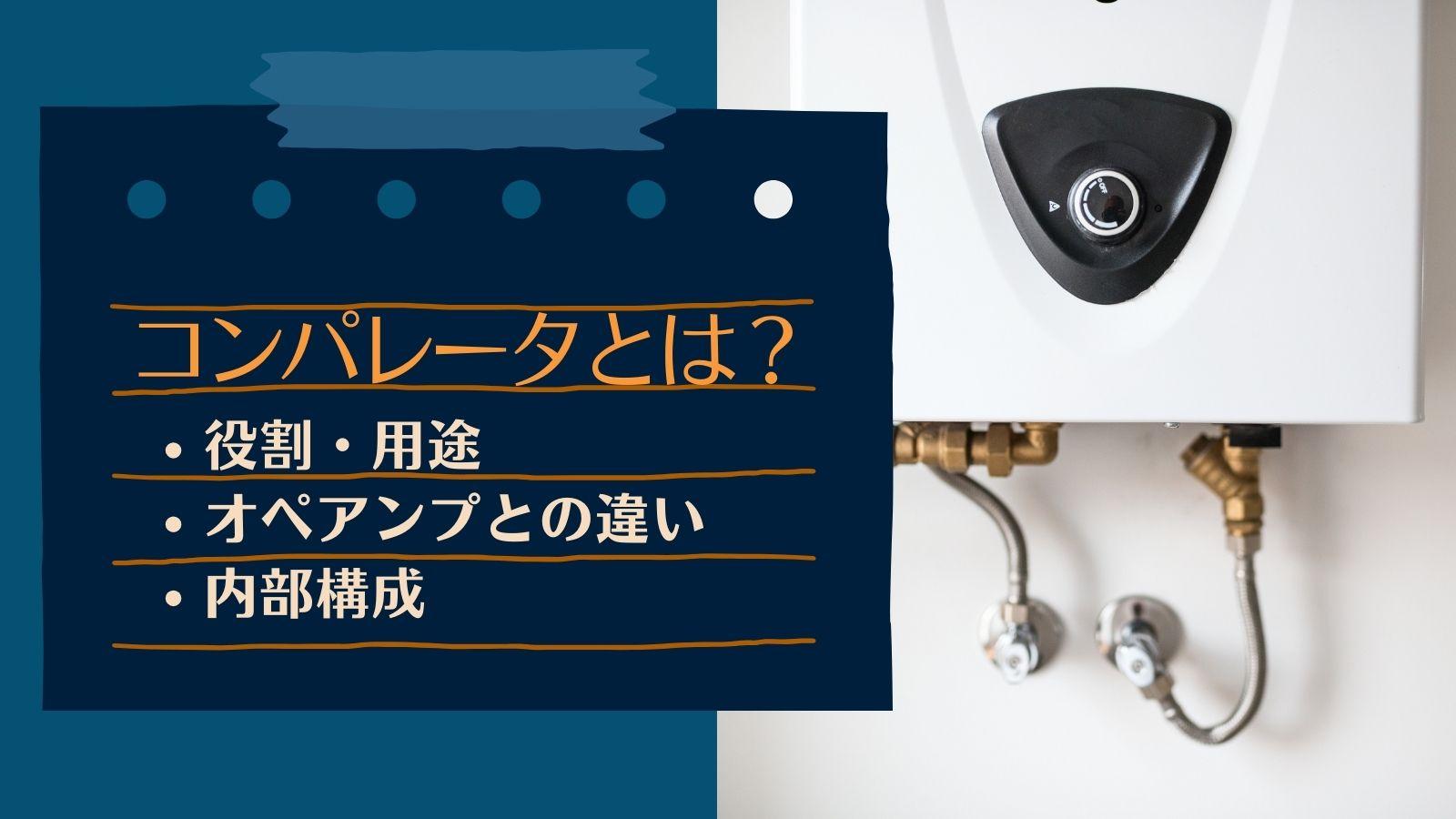
電子回路の中では、アナログ信号をデジタル的に扱いたい場面が多くあります。 例えば、「電圧が基準より高いか?低いか?」を判定し、ON/OFFを決めたり、 「一定の温度を超えたらファンを動かす」といった制御が必要になります。
そのような場合にコンパレータは、アナログ信号を判定してデジタル信号(0/1)へ変換する役割を担います。
本記事では、コンパレータとは何か、役割やオペアンプとの違い、さらに内部の仕組みや実際の用途まで解説していきます。
コンパレータとは? 役割について
コンパレータとは、 2つの入力信号(アナログ電圧)を比較し、その大小関係に応じて出力をデジタル的(0/1)に変化させる回路またはICのことです。
| 状態 | 出力 |
| 入力信号(V+) > 基準信号(V−) | HIGH(1) |
| 入力信号(V+) < 基準信号(V−) | LOW(0) |
電子回路では多くの場合、センサーからの出力や電源電圧、信号波形など、連続的なアナログ信号を扱います。 一方、制御系(マイコンやロジック回路)は 0(LOW)と1(HIGH) のデジタル信号で動作します。
このアナログ信号とデジタル信号をつなぐ役割を果たすのが、コンパレータです。
具体的にコンパレータは、以下のような役割があります。
電圧の大小を判定:基準電圧と入力信号を比較し、大きいか小さいかを判断する
ON/OFF制御:判定結果に応じてリレーやトランジスタをON/OFFに切り替える
デジタル信号への変換:アナログ信号をデジタル的に扱えるようにする
範囲内/範囲外の検出:上限と下限を設けた「ウィンドウ判定」ができる
高速な判定:速い応答時間でリアルタイムな制御が可能
コンパレータとオペアンプの違い
コンパレータとオペアンプは混合されやすい回路です。混合されやすい理由は、回路図記号が同じで、内部構造が似ている点が挙げられます。
また、内部構造はどちらも「差動増幅器」 が基本構造のため、内部回路図もとても似ています。
コンパレータ
動作の基本は、入力信号の差を比較するのみです。差がある場合は即座に「0/1」へ出力を振り切ります。
フィードバックは基本的にないため、増幅動作は行いません(オープンループ動作)。
オペアンプ
オペアンプ(Operational Amplifier)とは、演算増幅器ともいい、 元々は「加算」「減算」「積分」「微分」などの数学的演算をアナログ回路で実現するために開発されました。
現在では演算用途に限らず、増幅器、フィルタ、信号処理など、幅広く使われています。
オペアンプはネガティブフィードバックをかけて、増幅範囲内で安定動作するのが基本です。
入力差が小さくても出力がその差に応じてリニアに変化します。フィードバックをかけずに使うと、コンパレータとして動作させることも可能ですが、用途によっては不向きです。
コンパレータとオペアンプの違いについては、以下にまとめました。
| コンパレータ | オペアンプ | |
| 主な用途 | 電圧の大小を比較(判定) | 電圧の増幅 |
| 動作領域 |
飽和領域 (出力は0VまたはVcc付近に振り切れる) |
増幅範囲内で動作
|
| フィードバック | 基本なし |
ネガティブフィードバックをかけて安定動作
|
| 出力形式 | オープンコレクタ/プッシュプル | プッシュプル |
| 用途例 | しきい値検出、ゼロクロス検出、PWM生成 |
信号増幅、フィルタ、積分、微分
|
| 出力電圧の安定性 | 飽和領域に入りっぱなしで安定 |
ネガティブフィードバックで安定した電圧を出力
|
コンパレータの用途例
電圧監視(過電圧・低電圧検出)
電源電圧やバッテリー電圧が 設定した基準値を超えたか、下回ったかを判定します。
異常時にはアラームや保護動作を行います。
温度しきい値検出
サーミスタを使って、 一定温度を超えたかどうかを判定します。サーミスタの抵抗が温度によって変わり、分圧比が変化すると、コンパレータでしきい値判定が行われます。
例えば、温度が高いとファンがONとなったり、高温時に警告したり、オーバーヒート時に加熱を停止するといったことが可能です。
センサー信号のデジタル変換
光、音、振動などのアナログセンサー信号を 0(OFF)/1(ON)のデジタル信号に変換します。
ゼロクロス検出
交流(AC)の電圧が0Vを横切る瞬間を検出します。
高速動作や雑音防止の役割があるので、位相制御やインバータ駆動で使用されます。
コンパレータICの内部構成と各ブロックの動作
基本的なコンパレータICは、以下のブロックで構成されています。
差動増幅器
Vin+(非反転入力)と Vin-(反転入力)の電圧差を検出します。わずかな差でも大きな電圧差に増幅し変換可能です。
基本はバイポーラトランジスタ、またはMOSFETの差動対が使用され、さらに電流源が付いていれば増幅度が安定化します。
■動作
V+ > V- の場合、片側のトランジスタがON → プラス側から出力
V+ < V- の場合、もう一方のトランジスタがON → マイナス側から出力
※ この時点ではまだ小さな電圧差
カレントミラー(アクティブ負荷)
差動対の出力電流を高インピーダンス負荷で受けることで、増幅度を高めます。カレントミラー回路(対称的なトランジスタ配置)で電流を反転・増幅させます。
差動増幅器単体よりも出力の振れ幅を大きくでき、消費電力も抑えられます。
レベルシフタ
差動増幅器の出力を「出力段で扱える電圧範囲」に変換します。主にエミッタフォロワ(バッファ)や電流スイッチで構成されます。
レベルシフタは、差動増幅器の出力レベルと、出力段が必要とする電圧範囲が異なるため必要になります。
出力段
増幅された電圧差に基づいて、出力を「0(GND)」または「1(Vcc)」にします。
オープンコレクタ型かプッシュプル型の形式で出力されます。
■オープンコレクタの場合
出力段のトランジスタ(NPNなど)がON → 出力はGNDへ引き込まれる(LOW)
トランジスタOFF → 外部のプルアップ抵抗でHIGH(Vcc)に
■プッシュプルの場合
HIGH側とLOW側のトランジスタが交互にON・OFF → 自力でHIGH・LOWを出力可



