オペアンプの反転増幅回路とは? 特徴や基本構成、仕組みについて解説
- 半導体用語集
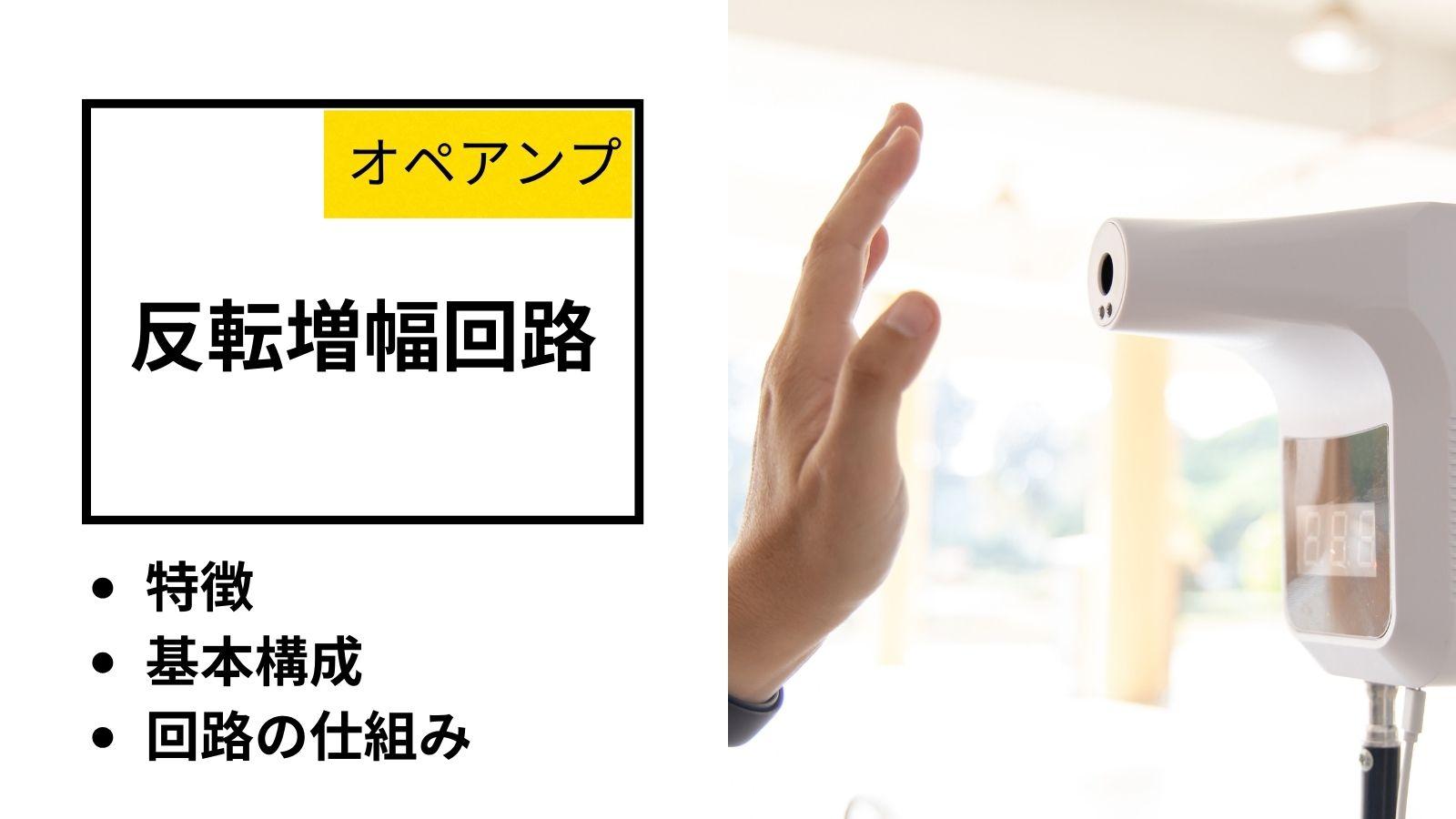
反転増幅回路は、オペアンプを使い、入力信号の向きを反転させながら、決まった倍率で信号を増幅する機能を持っています。
反転増幅回路は、構成がシンプルで設計もしやすく、精度の高い信号処理ができるため、センサー信号の前処理やアナログ演算回路など、さまざまな電子機器で活躍しています。
本記事では、反転増幅回路の特徴や構成部品、回路の仕組みなどを解説します。
オペアンプの反転増幅回路とは? 特徴について
反転増幅回路とは、オペアンプ(演算増幅器)という電子部品を用いて構成される増幅回路の一種です。入力信号を反転(180度位相反転)させながら、一定の倍率で増幅します。
例えば、入力がプラス(+)だったら、出力はマイナス(–)になります。
増幅の倍率は、回路に使われている抵抗の比で決まります。
入力:+1V → 出力:−10V(10倍で反転)
入力:−0.5V → 出力:+5V(10倍で反転)
このように、向きが逆になって、しかも何倍かの大きさになるのが特徴です。
電圧増幅率(ゲイン)は、Rf(帰還抵抗)とRin(入力抵抗)の比率で簡単に設定できます。
式:Av=Rf/Rin
増幅率の調整が簡単だと、回路設計がしやすいメリットがあります。
その他の特徴
入力インピーダンスが比較的低い
反転増幅回路では、入力信号がまずRinを通って回路に入るようになっています。そのため、回路の入口のインピーダンス(電気の通しやすさ)は、Rinの値とほぼ同じになります。
値はそれほど高くないので、高インピーダンスが必要な信号には向いていません。例えば、センサーなど微弱な信号源を扱うときには、非反転型の回路の方が適しています。
出力インピーダンスが非常に低い
オペアンプの出力側は、インピーダンスがとても低くなっています。つまり、出力先にしっかり電流を送れるということです。
電流をしっかり送れることで、次の回路や負荷をしっかり駆動できるので、信号の伝送や増幅後の処理に適しています。
直線性が良く、信号を正確に増幅できる
入力と出力の電圧が比例関係になります。
つまり、入力電圧を2倍にすれば、出力電圧もちょうど2倍になるということです。
例えば、増幅率が −10の回路なら、以下のようになります。
入力 +0.2V → 出力 −2V
入力 +0.4V → 出力 −4V
比例関係により信号がゆがまず、正確に再現されます。
ノイズに強く、安定した動作
反転増幅回路では、ネガティブフィードバックという仕組みを使っています。ネガティブフィードバックとは、出力の一部をオペアンプの「−」端子に戻すことで、オペアンプが常に出力をちょうどよく調整し続ける仕組みです。
そのおかげで、電源電圧の変動や部品の誤差や温度変化、外からのノイズといったさまざまな影響を自動で補正でき、回路が安定して動作します。
アナログ演算やセンサー信号の前処理に活用される
反転増幅回路は、単に信号を大きくするだけでなく、さまざまなアナログ演算回路の基本ブロックとしても活用されます。
例えば、加算回路や減算回路の構成要素として、複数の信号を加算・減算するような回路を作れます。電圧の時間変化に応じた演算処理にも使われます。
反転増幅回路の基本構成と回路の仕組み
反転増幅回路は、以下の部品で構成されます。
Vin(入力電圧):信号を加えるところ
Rin(入力抵抗):入力信号の電流を制限
Rf(フィードバック抵抗):出力を一部戻すことで、増幅の制御を行う
オペアンプ(演算増幅器):回路の中心的な働きをする部品で、信号を増幅する
GND グラウンド(接地):電気的な基準点
回路の仕組み
1. 入力信号(Vin)は、Rinを通ってオペアンプの「−」端子に入る
「−」端子は、回路の中心となる場所で、ここで信号処理が始まります。
2. 出力(Vout)は、Rfを通して同じく「−」端子にネガティブフィードバックされる
ネガティブフィードバックとは、再び「−」端子にオペアンプの出力を一部戻すことで、回路を安定させることをいいます。
3. オペアンプは「+」端子と「−」端子の電圧差がゼロになるように動作する
オペアンプの「−」端子と「+」端子の電圧差がゼロになるように出力を調整する特性によって、回路はバランスを取ろうとします。
4. その結果、「−」端子の電圧は仮想的に0V(仮想接地)となる
実際に接地していないのに、「−」端子は0Vのような状態に保たれます。
これを「仮想接地」と呼びます。
5. 入力信号は、増幅されて反対の向き(反転)で出力される
入信号は、向きが反対(正⇔負)になって、しかも大きな電圧に増幅されて出てきます。
反転増幅回路の主な用途
1. センサー信号の増幅
センサーから出力される信号は、電圧が非常に小さいことが多いため、そのままでは扱いにくい場合があります。
そんなとき反転増幅回路は、小さな信号を正確に増幅して、次の回路へ渡すために重要です。
例:温度センサー、圧力センサー、光センサーなど
2. オーディオ回路(音声信号の増幅)
マイクや楽器などからのアナログ音声信号を増幅して、スピーカーや録音装置へ送ります。高い直線性と低ゆがみが求められる音響機器に適しています。
3. アナログ演算回路の構成要素
加算回路や減算回路、積分回路や微分回路などのアナログ演算回路は、反転増幅回路をベースに構成されることが多いです。
計測機器や制御回路で、アナログ信号を数学的に処理する用途に使われます。
4. アクティブフィルタ回路
抵抗・コンデンサと組み合わせることで、特定の周波数だけを通す・遮断する回路(ローパスフィルタ、ハイパスフィルタなど)を作れます。
反転増幅回路を使うことで、ゲイン調整付きのフィルタにすることが可能です。
5. A/D変換の前段回路
アナログ→デジタル変換器(ADC)は、特定の電圧範囲でしか動作しないため、入力信号を調整する必要があります。
反転増幅回路は信号レベルを調整し、ADCが扱いやすい形に変えることが可能です。



