水晶振動子とは? 役割や圧電効果の仕組み、用途を解説
- 半導体用語集
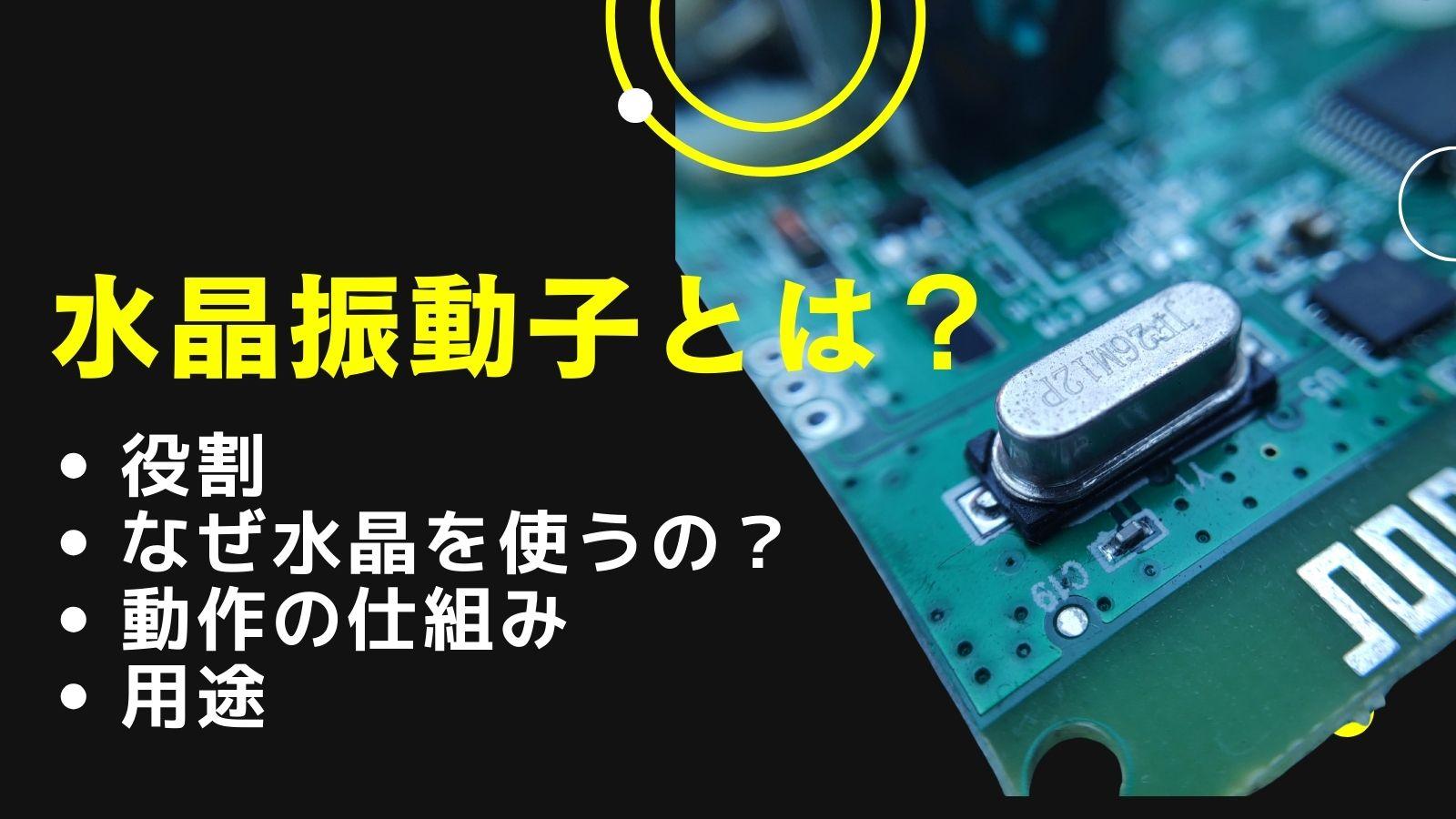
水晶振動子は、電子機器が正確なタイミングで動作するために必要な電子部品です。例えば、時計が1秒を数えたり、コンピュータの中でプログラムが正しい順番で動作させるために利用されます。
本記事では、水晶振動子の仕組みや基本構造、水晶発振器との違い、用途について解説していきます。
水晶振動子とは? 圧電効果と基本的な役割
水晶振動子(crystal resonator)とは、水晶(クォーツ)の圧電効果を利用して、安定した周波数の振動を発生させる電子部品です。
圧電効果とは、一部の結晶に圧力を加えると電圧が発生する現象、またはその逆に、電圧を加えると形が変わる(伸び縮みする)現象をいいます。
水晶振動子ではこの2つの性質を利用しており、まず水晶に電圧を加えることで振動を生じさせ(逆圧電効果)、その振動から電気信号を取り出す際には正圧電効果が働いています。
水晶振動子には、以下のような役割があります。
正確なクロック(周波数)を提供する
水晶振動子は、圧電効果によって特定の周波数で振動します。その振動を利用し、電子回路に安定したタイミング信号(クロック)を供給します。
例えば、通信機器はクロック信号によって、データを正確なタイミングで送受信できるようになります。
時間・周波数の基準になる
デジタル機器は、時間や周波数を測る必要があります。水晶振動子は高精度なため、機器全体の時間的な基準となります。
例えば、周波数カウンタや測定器で基準信号として利用されます。
安定性と信号の揺れの少なさを提供
水晶振動子は高いQ値を持つため、発振周波数のブレやノイズが小さいです。Q値(Quality factor)とは振動の鋭さ・純度を表します。
Q値が高いことで、通信やオーディオなど精度やノイズに敏感な回路でも安定動作が可能になります。
外部クロック源として機器を同期させる
機器同士を同期させる際にも、水晶振動子が発生する基準信号が利用されます。
通信機器やCPU、デジタル信号処理(DSP)などで、複数の装置が同じタイミングで動作するための共通リズムとして必要になります。
水晶振動子の基本構成・動作の仕組み
基本構成
水晶振動子は、主に水晶片と電極で構成されています。
水晶片
振動の主役となり、圧電効果を持つ天然または人工の水晶です。特定の角度でスライスされ、共振周波数が決まります。
電極
水晶に電圧を加えたり、振動から電気を取り出すための導電層です。金属蒸着や薄膜で形成されています。
振動の仕組み
水晶振動子は、以下のようにして動作します。
1. 電極に交流電圧を加える
2. 水晶が圧電効果で変形・振動する
3. 特定の周波数で共振(自然振動)
4. 振動により交流電圧が再び発生する
5. 電極から外部回路に信号として取り出される
このサイクルを、発振回路と組み合わせて持続させることで、安定したクロック信号が得られます。
なぜ水晶が使われるのか? 材料としての特性
水晶が電子回路で振動子として選ばれる理由は、圧倒的な「周波数安定性」と「信頼性」にあります。
圧電効果が利用できる
水晶は圧電体(ピエゾ電気体)という特別な材質のため、圧電効果があります。圧電効果によって、水晶は高精度な周波数を発生するための共振素子として使えます。
共振特性が非常に鋭く、Q値が高い
水晶はとても高いQ値を持つため、周波数の安定性に優れています。ブレが小さいと、フィルタや発振回路でノイズに強く、ピンポイントで周波数が決まることを意味します。
温度特性が優れている
温度が変化するとほとんどの材料の共振周波数が変動しますが、水晶は特定のカット方法によって、温度変化による周波数変動を最小限に抑えられます。
例えば、ATカット水晶は常温付近で温度係数が安定します。温度特性が良いため、周波数変動は最小限です。
ATカットとは、水晶の結晶を特定の角度でスライスしたものの名前です。「A」は結晶軸(X軸)のことで、「T」は角度(約35度15分)を表しています。つまり、X軸に対して35°15′傾けてカットした水晶板です。
加工性・コスト・信頼性がバランス良い
水晶は天然でも人工でも安価かつ大量生産できます。機械的・化学的に安定しており寿命が長いです。小型化にも適しており、SMD部品として表面実装も可能です。
周波数制御がしやすい
水晶のサイズや厚み、カット角度を変えることで、設計通りの周波数が得られるため、通信や計測用途でも高い信頼性があります。
水晶振動子の用途
水晶振動子は「正確な周波数(クロック)」を作るための共振器で、様々な電子機器の中でタイミングの基準として使われています。
単体では発振しないため、発振回路を内蔵したIC(集積回路)と組み合わせて使うのが基本です。
以下は代表的な用途です。
1. 時計・タイマー(リアルタイムクロック)
32.768kHzの水晶振動子がよく使われます。周波数は2¹⁵=32768 なので、2進数でカウントしやすく、1秒=1Hzに変換しやすいという特徴があります。
用途例:デジタル腕時計、電子レンジなどのタイマー、パソコンや家電のRTC(リアルタイムクロック)回路
2. マイクロコントローラのクロック源
8MHz、16MHz、20MHzなどの水晶振動子が使用され、マイコンの命令処理のタイミング(クロック)を提供します。正確なクロックが必要なとき、RC発振より水晶が利用されます。
3. 通信機器(無線・有線)
周波数が少しでもずれると通信ができないため、水晶の高精度が重要です。
用途例:Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、LTEなどの無線通信モジュール
4. 測定・計測機器
周波数カウンタ、タイマー、ストップウォッチなどで利用されます。周波数が基準の精度に直結するため、水晶振動子が多用されます。
水晶振動子と水晶発振器の違い
名前が似ている「水晶振動子」と「水晶発振器」は、役割と構成が大きく異なります。
水晶振動子(共振器)とは、音叉のようなもので、振動はするものの、それだけでは発振しません。必要に応じて、マイコンやICに内蔵された発振回路に組み合わせて使います。
水晶発振器とは、水晶振動子に発振回路を組み込んだものです。
電源をつなぐだけで発振器として動作し、安定したクロック信号を出力できます。製品には XO(一般発振器)、TCXO(温度補償)、OCXO(恒温槽)などの種類があります。



