集積回路とは? ICの特徴・役割・半導体との違いをわかりやすく解説
- 半導体用語集
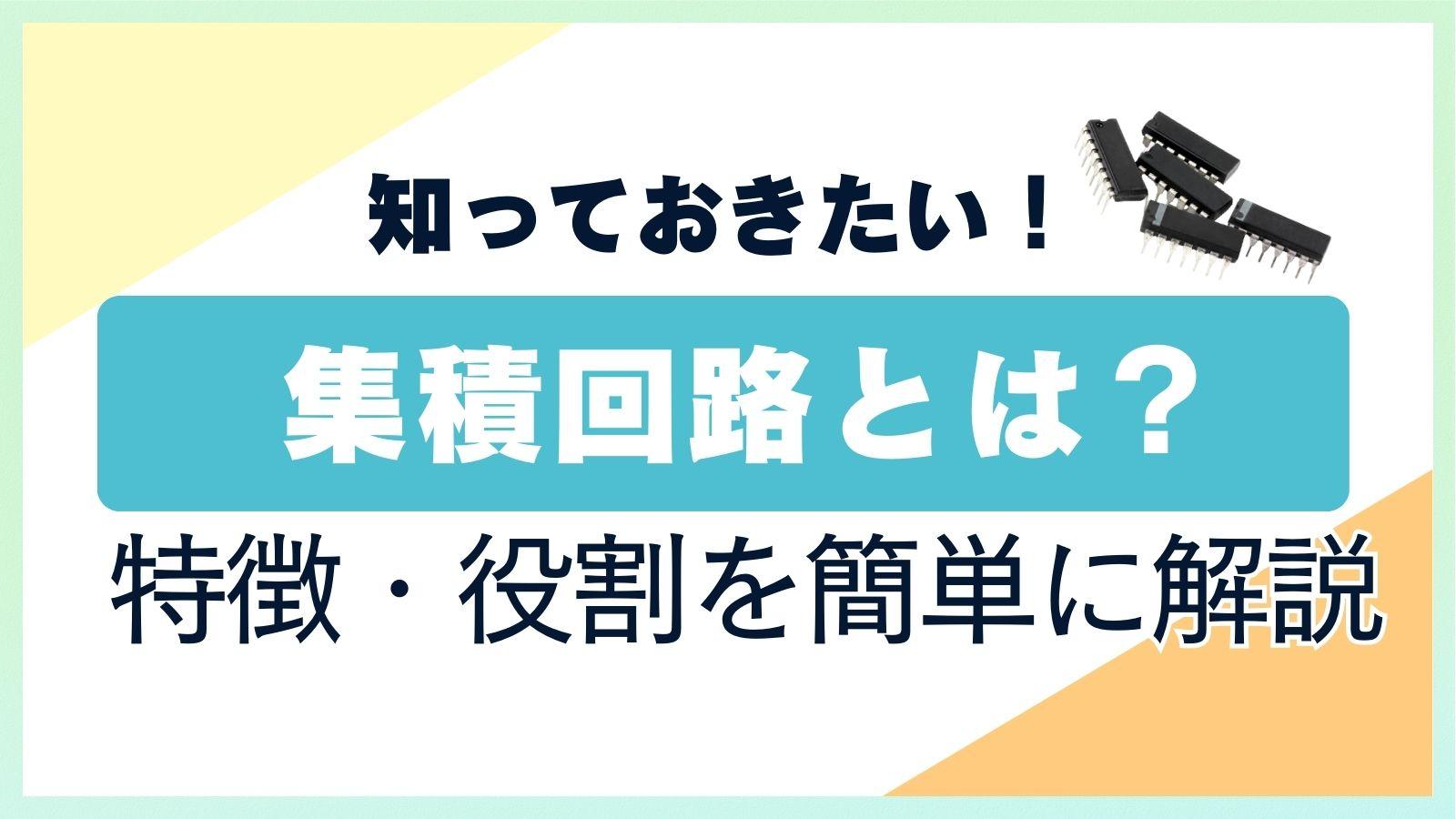
集積回路(IC:Integrated Circuit)は、スマートフォンやコンピュータの中核を担う小型の電子回路です。トランジスタや抵抗、コンデンサなどの部品を1つの半導体チップ上にまとめることで、複雑な処理を高速かつ省スペースで実現しています。
本記事では、集積回路の基本的な構造や特徴、役割、用途、半導体との違いなどについてわかりやすく解説します。
集積回路とは? 特徴と役割
集積回路(IC:Integrated Circuit)とは、複数の電子部品を1つの小さな半導体チップ上に集約して構成した電子回路のことです。
高密度な回路構成をしており、複数のトランジスタや抵抗などの素子を、わずか数ミリ四方のチップに高密度で集積しています。VLSI(超大規模集積回路)では、数十億個のトランジスタが入っていることもあります。
多数の電子部品を1つのチップに集約するため、とてもコンパクトになり、スマートフォンやウェアラブルデバイスなど、省スペースが重要な機器に最適です。
また、部品間の距離が短いため、電気信号の伝達が高速になり動作がスムーズです。そのため、コンピュータのCPUやGPUなど、高速処理が求められる場面に重宝されます。
デメリットは、IC内部は非常に小さく、密集して作られているため、一部が壊れても修理ができない点です。
一般的には、部品全体を交換する必要があります。また、高性能化・高密度化が進むほど発熱量が増加します。小型チップ内に熱がこもりやすく、冷却対策(ヒートシンク、ファンなど)が必要になるケースもあります。
最新のICは極めて微細な構造で作られており、設計・製造には高度な技術と設備が必要です。開発費用が高く、初期投資が大きくなりがちというデメリットがあります。
集積回路は何に使う? 用途について
集積回路は現代のほとんどの電子機器で活用されています。以下は主な用途例です。
スマートフォン・タブレット
SoC(System on a Chip):CPU、GPU、通信機能、カメラ制御などを1つのICに統合
メモリIC:RAMやフラッシュメモリ
電源管理IC(PMIC):バッテリーの制御
無線通信IC:Wi-Fi、Bluetooth、5Gなど
パソコン・サーバー
マイクロプロセッサ(CPU)
グラフィックチップ(GPU)
チップセット
ストレージIC
家電製品
マイクロコントローラ:動作制御やタイマー、センサーデータ処理
映像・音声処理IC
モーター制御IC
自動車(車載IC)
エンジン制御用IC(ECU)
ADAS(先進運転支援システム)用IC
センサIC(温度・圧力・加速度など)
EVのバッテリー管理ICやインバータ制御IC
集積回路と半導体の違い
集積回路(IC)と半導体は、似たような意味で使われやすいため混合されがちですが、集積回路(IC)は「製品や回路の構造」、半導体は「材料・材質」を意味します。そのため、両者の関係は「半導体で作られた高機能な回路=集積回路(IC)」となります。
ニュースなどで「半導体不足」といったことを耳にすることがありますが、これはICチップの供給不足を指していることが多いです。また、半導体メーカーの中には、ICを設計・製造している企業のことを指していることもあります。同じような意味合いで使用されることがあるため、混合して認識する人が多いといえます。
集積回路の歴史
集積回路(IC)の基礎となる「トランジスタ」は、1947年にアメリカのベル研究所で誕生しました。それまでの電子回路は、真空管を使って構成されていましたが、小型・省電力な電子部品としてトランジスタが誕生したことで、その後のICに大きな進歩を見せました。
1958年、テキサス・インスツルメンツ社のジャック・キルビー氏は、世界で初めてICの原型を試作しました。そして、翌年の1959年には、フェアチャイルドセミコンダクター社のロバート・ノイス氏が、シリコンとフォトリソグラフィ技術を用いてより実用的なICの製造方法を開発しました。
この2人の功績により、ICは実用化に向けて一気に進化していきます。その後、キルビー氏は2000年にノーベル物理学賞を受賞しています。
ICは当初、主に軍事・宇宙開発の用途で使用されていました。中でもNASAのアポロ計画では、軽量で高性能なICが重宝されました。これがきっかけとなり、ICの大量生産が始まり、価格も大きく下がっていきます。
集積度は年々向上し、SSI(Small Scale Integration)→ MSI(Medium Scale Integration)→ LSI(Large Scale Integration)→ VLSI(Very Large Scale Integration)と、段階的に進化していきました。
1965年、インテル社の共同創業者であるゴードン・ムーア氏は、「ICに集積されるトランジスタの数は18〜24か月ごとに倍増する」と予測しました。これは「ムーアの法則」と呼ばれ、IC技術の発展スピードを象徴する指標として長らく現実の技術進化に合致してきました。微細化の進展により、ICはより小さく、より高速で、より多機能になっていきました。
21世紀に入ると、ICは「System on a Chip(SoC)」という形でさらなる進化を遂げます。SoCはCPU、GPU、メモリ制御、通信機能などを1チップに統合し、スマートフォンやタブレット、IoT機器に広く採用されています。
集積回路の基本構造
集積回路(IC)は、主に層構造と機能ブロックで構成されています。
層構造
1. シリコン基板(Substrate)
ICの土台となる部分です。高純度の単結晶シリコンで作られており、この中にトランジスタなどのアクティブ素子が作り込まれます。
2. トランジスタ層(アクティブ領域)
集積回路の心臓部です。一般的にはMOSFETがぎっしり配置されており、電気信号のスイッチングや増幅を担います。その他、数十億個のトランジスタが配置されることもあります。
3. 配線層(メタル層)
トランジスタや回路ブロックをつなぐための金属配線が形成された層です。配線は多層構造(5層〜15層以上)で、上から見ると入り組んだ構造になっています。
4. 絶縁層(酸化膜など)
配線やトランジスタ同士が電気的に干渉しないように隔離する層です。主にシリコン酸化膜(SiO₂)などが使用されます。
5. パッケージ(外装部)
一般的に目にすることが多い「黒いチップ」の部分です。中のICチップを物理的に保護し、外部の端子(ピン)とつなげるための構造をしています。
表面はプラスチック樹脂、内部は金線や銅ワイヤーなどで接続されています。
機能ブロック
機能ブロックとは、IC内部にある特定の機能を持つ回路のまとまりを指します。
主に以下のような機能ブロックがあります。
| ICの種類 | 例 |
|---|---|
| マイコン(マイクロコントローラ) | CPU、RAM、タイマ、I/O、ADC、通信機能など |
| SoC(System on a Chip) | CPU、GPU、AIコア、メモリ、各種I/O |
| アナログIC | 増幅回路、基準電源、フィルタ回路など |
| メモリIC | メモリセルアレイ、デコーダ、制御ロジック |
集積回路の種類
集積回路(IC)の種類は、構造や集積度によって分類できますが、信号別に分けるとざっくり「デジタルIC」と「アナログIC」に分けられます。
デジタルICとは? 仕組み・役割
デジタルICとは、デジタル信号(=0と1の信号)を扱う集積回路です。デジタルICは電圧の状態で「0(オフ)」か「1(オン)」を表し、0と1の組み合わせで計算・判断・記憶・通信などを行います。
仕組みについて簡単にいうと、デジタルIC内部には無数のトランジスタがあり、スイッチのようにON・OFFを繰り返します。その動作が論理ゲートとなり、複雑な処理を構成し、クロック信号(一定周期のタイミング)に従って、正確に処理が進みます。
デジタルICの種類は、「ロジックIC」と「メモリIC」に分けられます。
ロジックICとは、論理演算(AND、OR、NOT など)や制御処理を行うICです。コンピュータの演算部、家電の制御回路などに使用されます。
メモリICとは、データを一時的または永続的に保存するICです。コンピュータのデータ保存、プログラム格納などに使用されます。
一時的にデータを保存するメモリを「RAM(Random Access Memory)」といい、書き換えが不可または限定的な読み出し専用のメモリを「ROM(Read Only Memory)」といいます。その他、USBメモリやSDカードなどは、電源を切っても消えない書き換え可能な「フラッシュメモリ」と呼ばれます。
アナログICとは? 仕組み・役割
アナログICとは、アナログ信号(=連続的な電気信号)を扱う集積回路のことです。アナログ信号では、電圧や電流のなめらかな変化(波形)をそのまま扱います。
アナログICの役割を簡単にいうと、信号の増幅やフィルタリング、電圧の安定化、信号変換などがあります。
信号の増幅:小さなマイクの音声信号を大きくする(アンプ)
フィルタリング:ノイズを除去してきれいな信号にする
電圧の安定化:一定の電圧を出力する(電源IC)
信号変換:アナログとデジタルの変換
アナログICには、オペアンプや電圧レギュレータなどがあります。オペアンプは微弱な信号を高精度に増幅できるため、マイク回路などで活用され、電圧レギュレータは出力電圧を一定に保つため、電源回路などで使用されます。
現代の回路では、デジタルICとアナログICが連携して使用されることが一般的です。例えば、温度センサの信号(アナログ)を読み取って、デジタル制御で冷却ファンを動かすというような動作を行えます。
トナリズムの取り扱いメーカー
半導体商社トナリズムでは、集積回路を製造・提供している半導体メーカーの情報を掲載しています。
詳しくは、以下よりご覧ください。



