スプリッタとは? 光・ビームの役割・種類別の動作原理を解説
- 半導体用語集
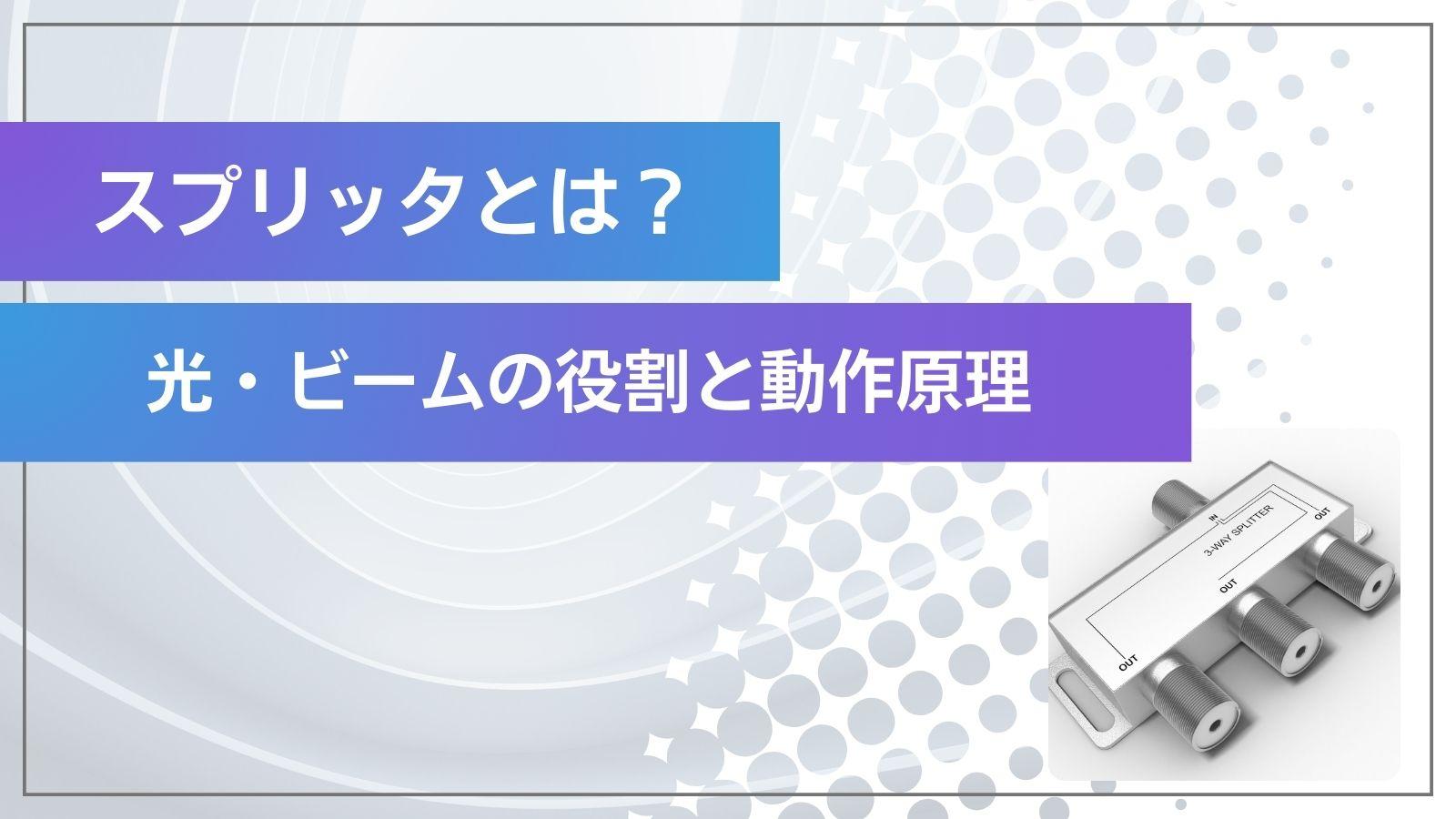
スプリッタとは、簡単に言うと「信号を効率よく分配する技術」です。
1つの信号を複数の経路に分けることで、ネットワークや光通信、映像機器、測定システムの構成をシンプルかつ効率的に保つために使われています。
本記事では、スプリッタの基本的な役割から、光スプリッタやビームスプリッタの種類ごとの特徴、構造、動作原理について解説します。
スプリッタとは?
スプリッタ(Splitter)とは、一つの入力信号を複数の出力に分配するためのデバイスや回路のことです。用途によって様々な種類があり、光通信、無線通信、オーディオ・映像機器、ネットワーク通信など幅広い分野で使用されます。
スプリッタを使って信号を分配する理由は、一つの信号を複数のデバイスや経路で利用する必要があるためです。
例えば光スプリッタであれば、1つの光回線を複数のユーザーに共有するために分配が行われます。個別に回線を敷設するより、1本の回線を分配するほうが効率的なのでコスト削減に役立ちます。
光スプリッタの役割・動作原理
光スプリッタ(Optical Splitter)とは、1本の光信号を複数の出力に分配する光学デバイスです。
主に光ファイバー通信(FTTH、PON、データセンター)や光計測、センサー技術で使用されます。
代表的な用途
FTTH(Fiber to the Home) → 光回線を各家庭に分配
PON(Passive Optical Network) → 1本の回線を複数のユーザーへ
データセンター → 大容量通信のネットワーク分岐
光計測・干渉計 → 光波を分割し測定・分析
光スプリッタの種類
PLC(Planar Lightwave Circuit)スプリッタ
・半導体製造技術を利用した高精度スプリッタ
・温度変化に強い
・均一な分配比(1×2、1×4、1×8、1×16、1×32など)
・FTTHやデータセンターで標準的に使用
動作原理
シリコン基板上に作られた光導波路を利用して、光信号を分岐させる構造です。
1. 光信号の入射
入力光ファイバーから光が導波路に入射します。
2. 光導波路内での分岐
分岐回路(Y字型やマッハ・ツェンダー干渉計型)を利用し、光を均等に分配します。導波路内での干渉効果を利用して、光エネルギーを等分または特定の比率で分配させることが可能です。
3. 出力ポートへの光信号の伝送
分岐した光は、各出力ポートへ均等に送られます。
例:1×2スプリッタ → 各ポートへ50%ずつ、1×4スプリッタ → 各ポートへ25%ずつ
FBT(Fused Biconical Taper)スプリッタ
・光ファイバーを熱で融合して作成
・分配比の調整が可能(例えば、70:30や50:50など)
・小規模ネットワーク向け(1×2、1×4など)
動作原理
2本以上の光ファイバーを加熱しながら引き伸ばし、テーパ(細くなる部分)を作ることで光を分岐させる仕組みです。
1. 光ファイバーの加熱と引き伸ばし
2本以上の光ファイバーを高温(約1,300℃)で加熱しながら引き伸ばし、接触する部分を徐々に融合させます。
2. 光の分岐
テーパ部(引き伸ばされた細い部分)では、光が隣接するファイバーに少しずつカップリングされ、分配されます。ファイバーを引き伸ばす長さや形状によって、光の分配比を調整可能です(例えば、70:30や50:50)。
3. 出力ポートへの光信号の伝送
分岐した光は、設定された比率で各出力ポートへ送られます。
ダイクロイックスプリッタ(Wavelength Selective Splitter)
・特定の波長のみを分配(波長分割多重 WDM用)
・複数の波長で同時通信が可能
・異なる波長の光信号を分ける、まとめる
・データセンターや光通信インフラ向け
動作原理
特定の波長の光を分離・合成するために用いられます。異なる波長の光を特定の経路に分けるため、フィルターを使用します。
1. 異なる波長の光信号を入力
例:1,310nmと1,550nmの光信号を1本のファイバーで伝送
2. ダイクロイックミラーや光フィルターを使用
特定の波長を透過、他の波長を反射するフィルターを利用して光信号を分離させます。
3. 分離された光を出力ポートへ送信
例:1,310nmの光はAポート、1,550nmの光はBポートへ
ビームスプリッタとは? 役割・動作原理
ビームスプリッタ(Beam Splitter)とは、入射した光を2つ以上の異なる経路に分割する光学素子です。光の透過と反射を利用して、干渉計測、レーザー光学システム、光通信、映像技術などで広く使用されます。
代表的な用途
干渉計測 → 2つの光経路を作り、干渉パターンを測定。科学研究や天文学で利用
レーザー測定・光学機器 → レーザー光を分割し、精密な測定や光学実験に利用。リソグラフィー(半導体製造)にも応用
映像技術(プロジェクター・VR/AR)→ RGB光の分離・合成。3Dディスプレイ技術
種類【構造別】
ビームスプリッタを構造別に種類を分けると、キューブ型とプレート型に分類できます。
キューブ型ビームスプリッタ(Cube Beam Splitter)
キューブ型ビームスプリッタとは、2つの直角プリズムを接着して作られたビームスプリッタで、入射した光を反射光と透過光の2つに分割する光学デバイスです。
S偏光とP偏光に対する反射・透過の差をできるだけ小さくするために設計されています。ただし、一部の設計では偏光依存性が発生する場合もあるため、高精度な用途では偏光コントロールが重要です。
プレート型ビームスプリッタ(Plate Beam Splitter)
プレート型ビームスプリッタとは、薄いガラスプレートに半透明のビームスプリッティングコーティングを施した光学素子です。光を透過と反射に分割する働きを持ちます。
動作原理(キューブ型・プレート型)
1. 光の入射
単一の光ビームがキューブの1つの面(入射面)から入ります。
2. ビームスプリッティングコーティングによる分割
入射した光が、キューブ内部のビームスプリッティングコーティングに到達します。コーティングにより、一部の光は透過し、一部の光は反射されます。
通常は50:50の比率で分割(その他の比率も可能)。
3. 透過光と反射光の分離
透過光は入射角と等しい角度で反射し、キューブの側面から出射します。
この原理により、1つの光源を2つの異なる光経路に分割できます。
種類【光学特性別】
偏光ビームスプリッタ(PBS: Polarizing Beam Splitter)
偏光ビームスプリッタとは、光の偏光状態(S偏光・P偏光)に応じて光を分離するビームスプリッタです。光は電磁波の一種であり、電場(E)と磁場(B)が直交して伝わります。その中でも偏光とは、光の電場の振動方向が一定の特性を持つ状態のことを指します。
偏光ビームスプリッタでは、S偏光(垂直偏光)を反射し、P偏光(平行偏光)を透過する仕組みになっています。この特性を利用することで、光の経路を分離・制御できます。
主な用途
レーザー光学:S偏光・P偏光を分離して、光の制御や最適化を行う
光通信:偏光多重通信を利用し、データ容量を増加させる
動作原理
1. 非偏光の光がPBSに入射
入射光にはS偏光とP偏光が含まれています。
2. PBSの偏光分離膜に到達
偏光分離膜がS偏光とP偏光を選択的に分けます。
3. S偏光の反射
偏光分離膜で反射し、90°方向に出射します。
4. P偏光の透過
偏光分離膜を直進して透過します。
無偏光ビームスプリッタ(NPBS:Non-Polarizing Beam Splitter)
無偏光ビームスプリッタとは、S偏光とP偏光の両方をほぼ等しい比率で透過・反射するように設計されたビームスプリッタです。
一般的な偏光ビームスプリッタは、S偏光を反射し、P偏光を透過しますが、NPBSは偏光の影響を受けず、一定の比率(例:50:50)で光を分割できます。
動作原理
1. 光の入射
入射光は、S偏光とP偏光の成分を含んだ自然光やレーザー光です。通常の誘電体ミラーでは、偏光成分によって異なる透過・反射比率を示します。
2. 誘電体多層コーティングによる補正
NPBSのコーティングは、S偏光とP偏光の分離を抑えるように設計されています。具体的には、多層の誘電体膜を設計し、異なる位相補正を行うことで、S偏光とP偏光の透過・反射を均等にします。
3. 光の分割
S偏光とP偏光が入射光の偏光状態によって比率が決まり分割されます。反射光と透過光の強度が等しくなるように設計されているため、光路のバランスが保たれます。



