SSR(ソリッドステートリレー)とは? メリット・デメリット、動作の仕組み、EMRとの違いを解説
- 半導体用語集
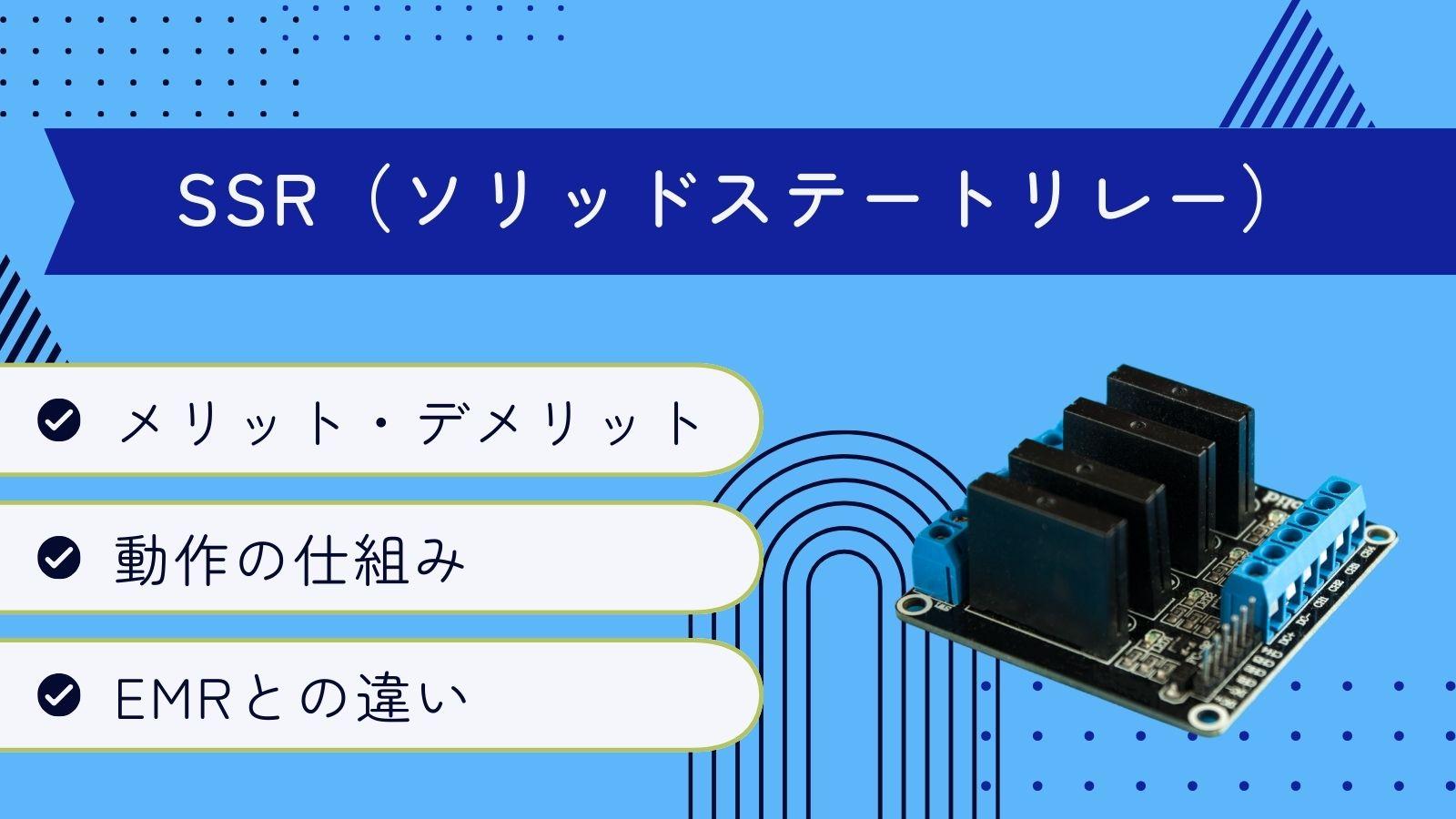
ソリッドステートリレー(SSR)は、半導体素子を利用した電子式のスイッチングデバイスです。特に、高頻度スイッチングが求められる機器や、電磁ノイズを嫌う環境での使用に適しています。
本記事では、動作の仕組みや特徴、メリット・デメリット、構成要素について詳しく解説します。
ソリッドステートリレー(SSR)とは?
ソリッドステートリレー(Solid State Relay, SSR)とは、可動部を持たない半導体素子による電子式のスイッチングデバイスです。従来の電気機械式リレー(Electromechanical Relay, EMR)と異なり、SSRはトライアック、サイリスタ、MOSFETなどの半導体デバイスを用いて負荷のオン・オフを制御します。
機械的な接点を持たず、光絶縁(フォトカプラ)を利用して制御信号を伝達することで、長寿命・高速スイッチング・低ノイズを実現します。
SSRのメリット
SSRは半導体素子を用いた電子的なスイッチなので、スイッチング速度が非常に速いのが特徴です。また、電磁的なスイッチング方式を使用しないため、スイッチング時の電磁ノイズがほとんど発生しません。
機械的な可動部がないため、摩耗の心配がなく、長期にわたり利用できます。また、機械部品が不要なため、コンパクトで軽量な設計が可能です。動作音がないため、静穏性が求められる環境に適しています。
SSRのデメリット・対策
SSRには以下のようなデメリットがあるため、対策が必要です。
発熱リスク
SSRは半導体素子の内部抵抗によりスイッチング時に発熱するため、放熱対策が必要になります。
対策:適切なヒートシンクや冷却ファンを使用する
突入電流に弱い
誘導負荷(モーター、トランス)や大電流負荷では、突入電流による故障リスクがあります。
対策:サージ吸収素子(バリスタ・スナバ回路を併用する)
オフ時の漏れ電流
SSRはオフ状態でも微小な電流が流れることがあります。
対策:完全遮断が必要な場合は補助回路を使用
SSRの主な構成要素
1. 入力部(制御回路)
外部からの制御信号を受け取る部分です。小さな電圧や電流でSSRをオン・オフします。
主な構成要素
フォトカプラ(光アイソレータ):SSRの入力部と出力部を電気的に絶縁する。光信号を用いるため、電磁ノイズの影響を受けにくいのがメリット
電流制限抵抗:LED駆動電流を適正に調整し、過電流を防ぐ
保護回路(ツェナーダイオードなど):過電圧や過電流による故障を防ぐ
2. 絶縁部(アイソレーション回路)
入力部と出力部を電気的に絶縁し、安全性を確保します。絶縁部により、ノイズ耐性を向上させ、誤動作を防ぎます。
主な構成要素
フォトカプラ(光アイソレータ):LEDとフォトトランジスタの組み合わせで、入力信号を光信号に変換して出力部に伝達する。電気的接続がないため、高耐圧絶縁が可能
高周波絶縁トランス方式:一部の高性能SSRでは、高周波トランスを用いた絶縁方式を採用。高速応答が可能で、高電圧環境でも安定動作
キャパシタ絶縁方式:光を使わずにキャパシタ結合で信号を伝達する方式。超高速スイッチングが可能
3. 出力部(スイッチング素子)
負荷側の電流をオン・オフ制御する部分です。SSRの種類によって、AC負荷用とDC負荷用で異なるスイッチング素子が使われます。
AC負荷用の主な構成要素
トライアック:AC負荷のスイッチングに使用される双方向性スイッチ。ゼロクロス回路と組み合わせて突入電流を抑える。家庭用機器(照明、ヒーター制御)でよく使われる
サイリスタ:一方向性のスイッチング素子。高電流・高耐圧の負荷に適している
DC負荷用の主な構成要素
MOSFET:低オン抵抗で高速スイッチングが可能。DC負荷の制御に最適
IGBT:高電圧・大電流のDC負荷に適している。インバータや電力変換装置向け
4. スイッチング補助回路
出力部のスイッチング特性を最適化し、安定した動作を確保します。突入電流対策やノイズ低減のための回路です。
主な構成要素
ゼロクロス回路:AC電流がゼロになる瞬間にスイッチングを行う回路。サージ電流を抑制し、負荷に優しい動作を実現。主にヒーターや照明のオン・オフ制御で使用
スナバ回路(RC回路):スイッチング時のサージ電圧を抑えるための回路。トライアックやサイリスタの誤動作を防止する。抵抗+ コンデンサの組み合わせが一般的
過電流保護回路:ヒューズやバリスタを併用し、過電流や雷サージからSSRを保護
ヒートシンク(放熱設計):半導体スイッチはオン時に発熱するため、放熱対策が必要
5. 外部インターフェース(オプション)
SSRの利便性を高めるための追加機能です。
主な構成要素
ステータスLED:SSRの動作状態(オン・オフ)を表示すると、配線ミスや動作確認がしやすくなる
ヒートシンクセンサ:一部の高性能SSRには、過熱を検出する温度センサーが内蔵
リモート制御・スマートSSR:IoT対応のSSRでは、マイコンやPLCと直接通信できる機能を搭載
SSRの動作の仕組み
SSRの基本動作の流れは以下の通りです。
1, 入力部(制御信号の受信)
外部の制御回路(PLC、マイコン、スイッチなど)からの信号を受け取ります。信号がONになると、SSR内部のLEDが点灯します。
2. 絶縁部(フォトカプラによる信号伝達)
LEDの光がフォトカプラ内のフォトトランジスタに当たり、出力回路を駆動します。光を介した信号伝達のため、入力と出力が電気的に絶縁されます。
3. 出力部(負荷のオン・オフ制御)
フォトトランジスタの信号を受け、半導体スイッチが動作します。そして、負荷(モーター・ヒーター・照明など)に電流を流す、または遮断します。
SSRとEMRの違い
EMR(電気機械式リレー)とは、電磁コイルと機械的な接点を使用して、電気回路のオン・オフを制御するスイッチングデバイスです。 電流をコイルに流すことで磁場を発生させ、可動接点を動かして回路を開閉します。
SSRとEMRはどちらも電気的なスイッチとして使われますが、動作原理・特性・用途が異なります。
| SSR | EMR | |
| スイッチング方式 | 半導体(トライアック、MOSFET)を使用 |
可動接点(電磁コイルと機械的スイッチ)を使用
|
| 駆動方式 | 光アイソレーションによる非接触スイッチング | コイルを励磁し、機械的接点を動かす |
| スイッチング速度 | 高速 | 遅い |
| 機械的摩耗 | なし(可動部がない) | あり(接点の摩耗が発生) |
| ノイズ | 低い(EMIが少ない) |
高い(接点のアーク放電によるノイズ)
|
| 発熱 | 高い | 低い |
| 電圧降下 | あり(半導体の内部抵抗による) | ほぼなし |
| 消費電力 | 低い(効率的) | 高い(コイルの消費電力が大きい) |
| 用途 | ・高頻度のスイッチング ・長寿命が必要なシステム ・静音・低ノイズ環境が必要な機器 |
・大電流や突入電流の対応 ・シンプルなオン・オフ制御 |



